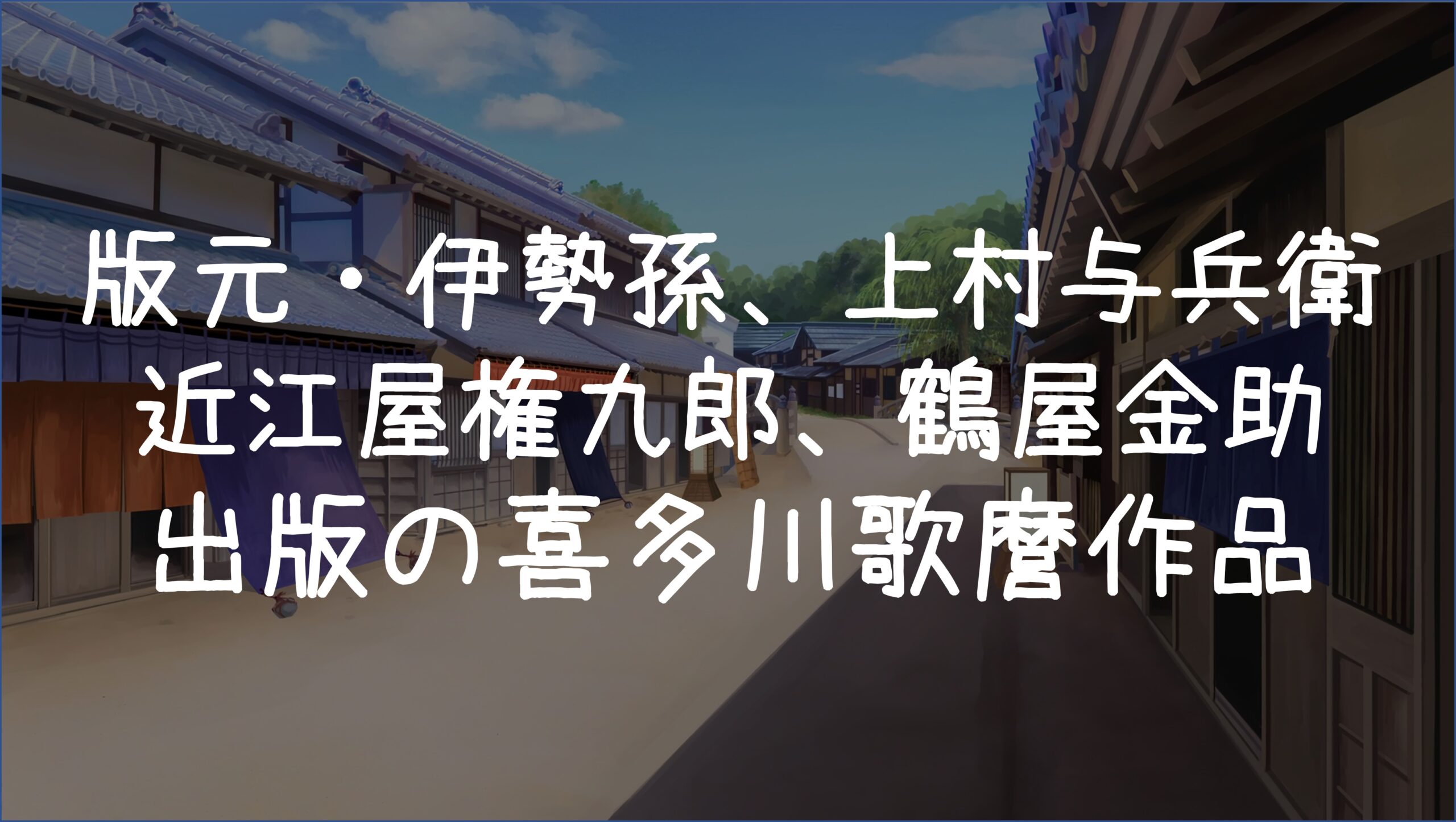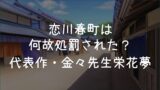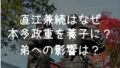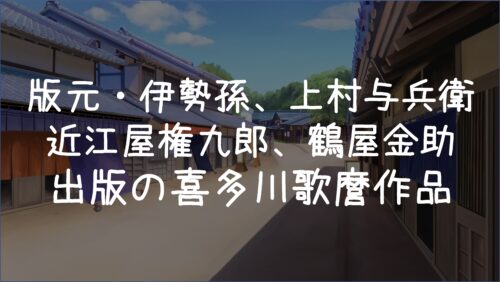
天明8年(1788年)から、版元・蔦屋重三郎とタッグを組み、美人大首絵を中心に次々と名作を世に送り出した喜多川歌麿。

他の版元が喜多川歌麿を放っておくわけはありません。
寛政6年(1794年)、蔦屋重三郎が東洲斎写楽と共に役者絵の出版に乗り出すと、喜多川歌麿は他の版元と一緒に仕事を始めます。
版元・伊勢孫、上村与兵衛、近江屋権九郎、鶴屋金助出版の喜多川歌麿の作品を紹介します。
版元・伊勢孫の「北国五色墨」
版元・伊勢孫から出版された「北国五色墨」。

北国とは江戸の北に位置する吉原を指します。
おいらん、芸を売る芸妓の他、最下級の遊女である川岸、てっぽう、切の娘が描かれています。
立場は違えど、同じ吉原で生活する女性の生き様に迫った作品です。
版元・上村与兵衛の「針仕事」
版元・上村与兵衛から出版された「針仕事」。
① 紅色の絞り染めの布の両側を持つ、眉を剃った既婚女性と若い女性
② 虫かごを眺める若い女性
③ あられ模様の絽の布を透かして見る若い母親
④ 母親に甘える幼子
など、日常の光景を一枚に描いた作品です。
版元・近江屋権九郎
版元・近江屋権九郎の出版物は3作品紹介します。
「五人美人愛敬競 松葉屋喜瀬川」
版元・近江屋権九郎から出版された「五人美人愛敬競 松葉屋喜瀬川」。
「八重毛」と呼ばれる櫛ですいた複雑な髪の流れを表現した、喜多川歌麿のこだわりが見られる作品です。
描かれた松葉屋喜瀬川の名前は判じ絵で示されています。
「見立邯鄲」
版元・近江屋権九郎から出版された「見立邯鄲」。
「邯鄲」は恋川春町が黄表紙「金金先生栄花夢」として出版した謡曲でもあります。
盧生という男性が出世を願って楚に向かっていると、邯鄲で道士・呂翁に出会います。
呂翁から枕を借りて寝たところ、栄華の叶う夢を見ます。
ところが、目が覚めると、黄梁(アワ)はまだ煮えておらず、わずかな時間しか経っていません。
こま絵には、このような栄枯盛衰のはかなさが描かれています。
この図柄をもとに描かれたのは、御殿女中と共に輿で身請けされる夢を見ている遊女です。
「両国橋」
版元・近江屋権九郎から出版された「両国橋」。
大判錦絵の上下六枚続という贅沢な作品で、その大きな画面に橋の上下に集まる行楽の人々を描いています。

橋下からのぞく遠い岸辺に御船蔵が描かれていることから…
隅田川で最もにぎわっていた両国橋を描いていると考えられます。
また、青傘と呼ばれる日傘が描かれていることから…
夏の暑い時期を描いていると考えられます。
橋上では幼子を抱く母親を中心に、芸者や御殿女中など、さまざまな立場の女性が描かれています。
版元・鶴屋金助の「教訓親の目鑑」
享和2年(1802年)から、版元・鶴屋金助とタッグを組み、「教訓親の目鑑」シリーズを出版。
親の目から娘を観相し、娘の性格について、長い解説文が書かれています。
「教訓親の目鑑 俗ニ云ぐうたら兵衛」では、髷が崩れた、寝起き姿の娘が描かれています。
左手に茶碗、右手に房楊枝(歯ブラシ)と歯磨き粉の袋を持ち、肩に手ぬぐいをかけています。
だらしなく、前向きな気持ちが全く感じられない娘。
親の教えが行き届かないから、このような娘に育ったのだという教訓です。

「教訓親の目鑑 俗ニ云ばくれん」では…
左手にゆでた菱蟹を左手に、右手に酒の入ったギヤマンを持つ女性が描かれています。
まとめ:蔦屋重三郎以外の版元から出版された絵も見物!
版元・伊勢孫、上村与兵衛、近江屋権九郎、鶴屋金助出版の喜多川歌麿の作品を紹介しました。
蔦屋重三郎とはまた異なる作品を生み出した版元達。
版元に関係なく、喜多川歌麿が作品に真摯に向き合ったこともよく分かりますね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()