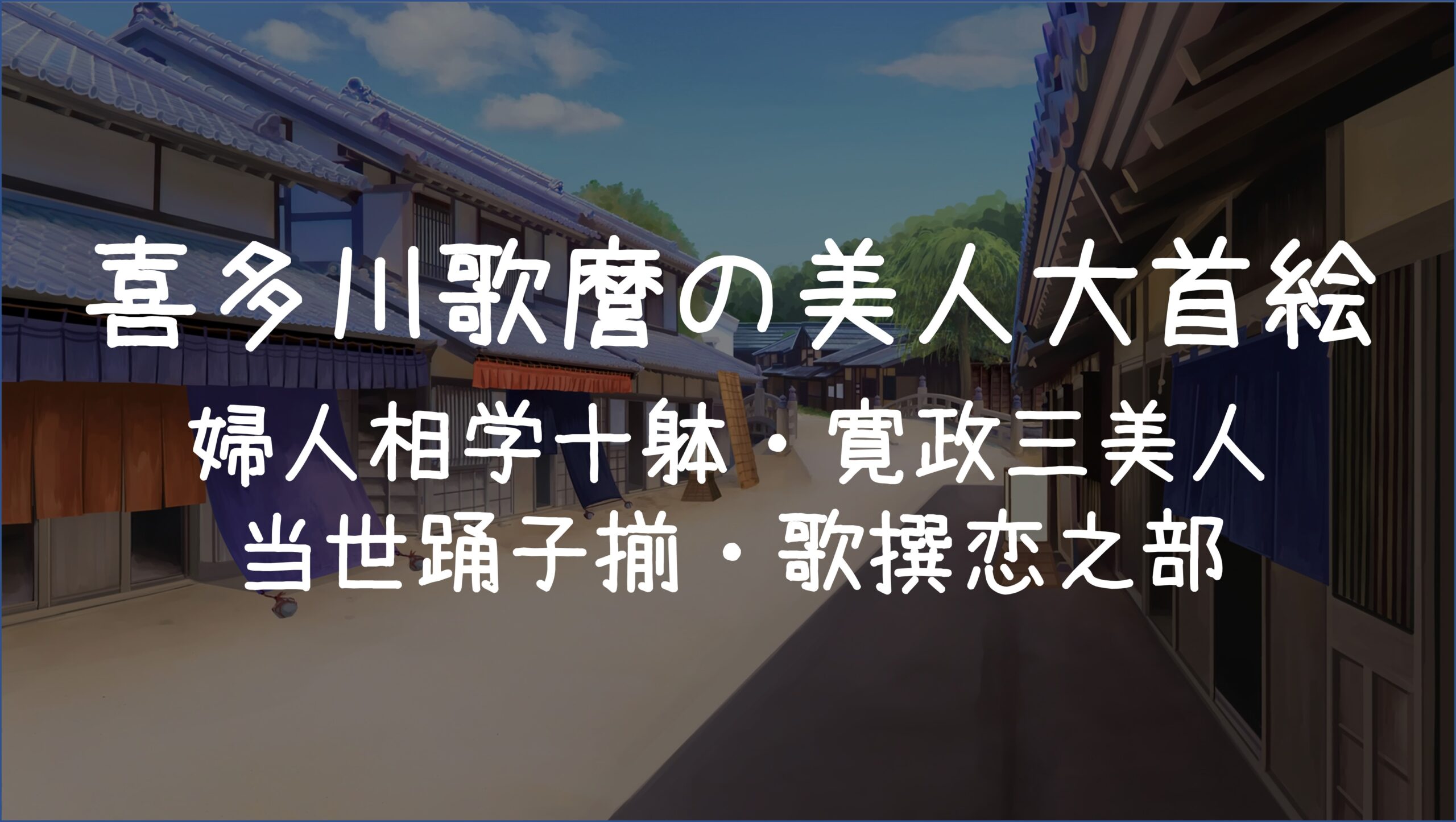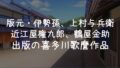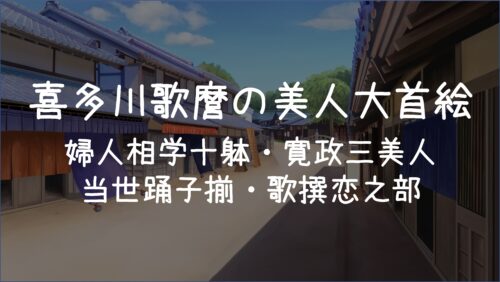
喜多川歌麿の代名詞・美人画の大首絵(おおくびえ)。
ブロマイドの需要が高かった役者絵では既に用いられていましたが、美人画で大首絵を用いる浮世絵師はいませんでした。
寛政4年(1792年)から寛政6年(1794年)にかけて、版元・蔦屋重三郎は喜多川歌麿の美人大首絵を出版します。
喜多川歌麿の有名な美人大首絵を4シリーズ紹介します。
婦人相学十躰
「相学」とは人相で人格を判断する学問。
女性の表情や仕草から人格を読み取り、それを10種類のタイプに分けて描いています。
婦人相学十躰(ポッピンを吹く女)
ガラス製のビードロ(ポッピン)を吸ったり、吹いたりしている女性を描いています。
描かれているのは、
☑ 根本を高く結った島田髷(まげ)
☑ 粋なかんざし
☑ 紅色の市松模様に小花を散らした振袖
というオシャレでありながら、あどけなさの残る女性です。
婦人相学十躰 浮気之相
サブタイトルの「浮気之相」から、複数の男性に心を揺さぶられる女性を描いていると考えられます。
☑ 簡単にまとめた髪
☑ 浴衣からはだける胸
☑ 肩にかけた手ぬぐい
が描かれていることから、女性は風呂上がりのようです。
寛政三美人
喜多川歌麿が描いた次の3人の女性は寛政三美人と呼ばれています。
②江戸両国薬研堀米沢町2丁目の煎餅屋・高島長兵衛の娘である高島おひさ
③吉原玉村屋抱えの芸者で富本節の名取であった富本豊雛
描いた女性が一目で判るよう、喜多川歌麿はそれぞれに紋(マーク)を入れています。
難波屋おきた
女性が難波屋おきただと一目で判るよう、喜多川歌麿は桐の紋を描いています。
例えば、「姿見七人化粧」。
黒襟の普段着を着て、鏡をのぞき込んでいる女性を描いています。
女性の後ろ姿、鏡に映し出された女性の顔を一枚で楽しめる作品です。
着物に白抜きで桐の紋が描かれているため、描かれている女性は難波屋おきただと判ります。
高島おひさ
女性が高島おひさだと一目で判るよう、喜多川歌麿は三つ柏の紋を描いています。
例えば、「高島おひさ」。
高島おひさの正面と後ろ姿が紙の表裏にぴったり重なるように描かれた珍しい作品です。
うちわと前掛けに三つ柏の紋が描かれています。
富本豊雛
女性が富本豊雛だと一目で判るよう、喜多川歌麿は桜草の紋を描いています。
例えば、「富本豊ひな」。
催事の案内と想像できる三つ折りの印刷物を手にした女性を描いています。
黒い着物に桜草の紋が描かれています。
当世踊子揃
吉原で活躍する芸者の舞踊姿を描いたシリーズです。
当世踊子揃 鷺娘
鷺娘は踊りのタイトル。
☑ 牡丹をあしらった花笠をかぶる
☑ 花笠をもう一つ持って踊る
☑ うつむいて首を少しかしげる
女性を描き、白鷺の精が白無垢衣装から町娘に変化する華やかな動きを表現しています。
当世踊子揃 吉原雀
鳥売りである八幡太郎義家と女鳥売りとなった鷹の精が登場する「吉原雀」。
指一本一本が丁寧に描かれていて、まるで踊り子が動いているようです。
歌撰恋之部
背景を紅雲母摺(べにきらずり)一色とした5枚シリーズ。
タイトルのとおり、恋をテーマにさまざまな立場の女性を描いています。
歌撰恋之部 物思恋
小鳥模様の小紋を着て、物思いにふける女性を描いています。
☑ 眉がないため、女性は既婚だと想像できること
☑ サブタイトルの「物思恋」
から、女性は夫ではない男性のことを考えているようです。
歌撰恋之部 夜毎に逢恋
ラブレターをこっそり読む女性を描いています。
眉はあるものの、鉄漿(お歯黒)をしていることから、若い既婚女性だと考えられます。
夜しか会えない恋人、つまり、夫以外の男性と会っているようです。
歌撰恋之部 あらはるる恋
恋心を隠そうとしても隠せない女性を描いています。
うちわに桜草が描かれているため、女性は富本豊雛かもしれません。
まとめ:喜多川歌麿の観察力と洞察力がスゴイ!
喜多川歌麿の有名な美人大首絵を4シリーズ紹介しました。
町で評判の美人を大首絵で魅力的に描けたのは、喜多川歌麿だからこそ。
喜多川歌麿の美人大首絵をプロデュースした版元・蔦屋重三郎の手腕にも注目ですね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()