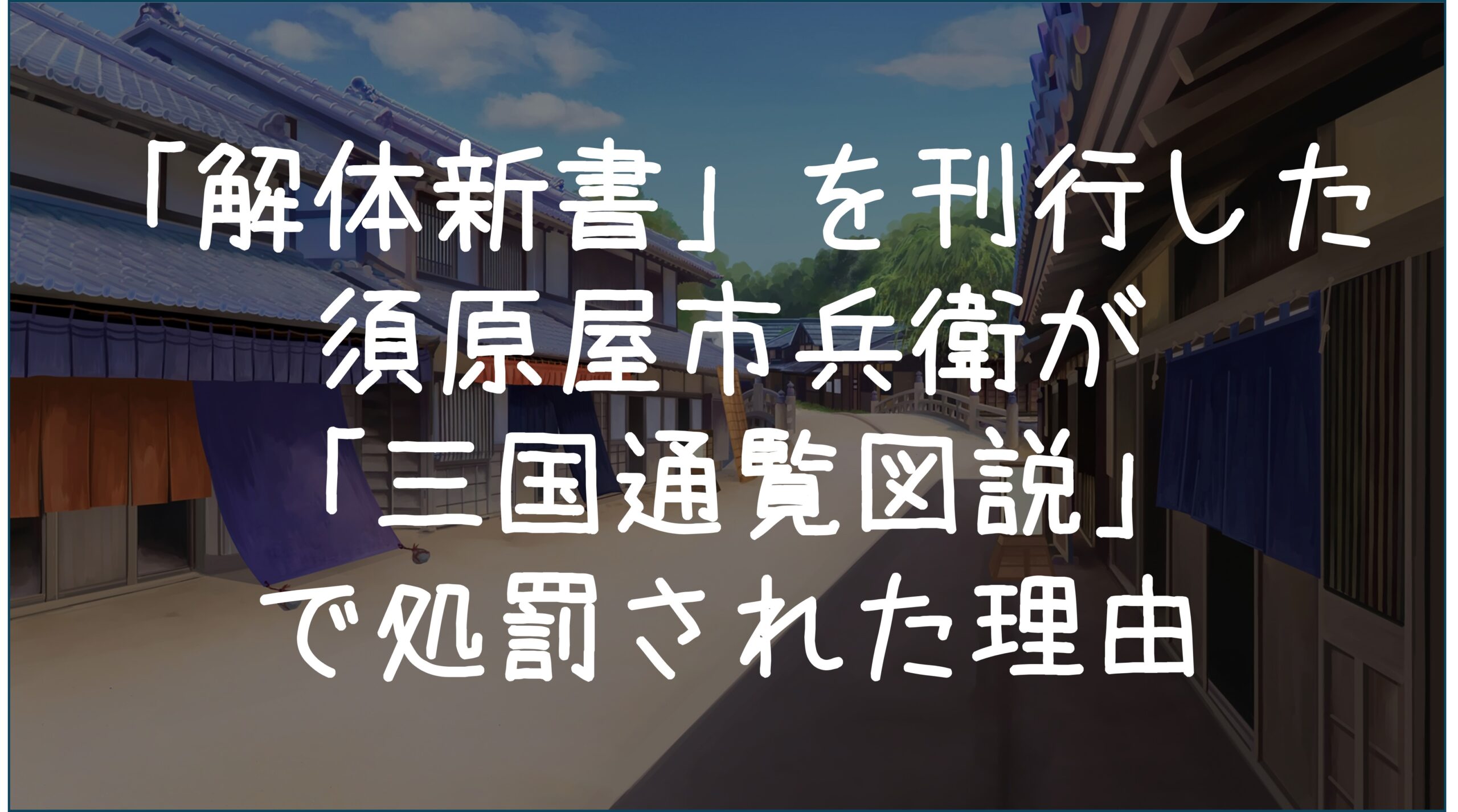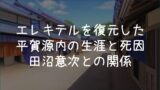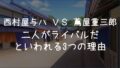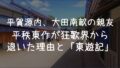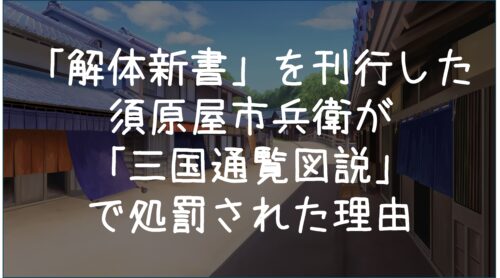
蔦屋重三郎と同じ時代を生きた版元・須原屋市兵衛。
ただ、須原屋市兵衛は学者の版元として、学術書や辞典などの刊行、販売を行いました。
須原屋市兵衛の生涯、「三国通覧図説」で処罰された理由を紹介します。
須原屋市兵衛ってどんな人?
須原屋市兵衛は版元であり、歴代店主の通称です。
江戸の出版業界最大手といわれる須原屋茂兵衛から暖簾分けした須原屋市兵衛。
日本橋室町三丁目に店を構えると、宝暦12年(1762年)に俳人・建部綾足の「寒葉斎画譜」を刊行しました。
平賀源内著「物類品隲」を刊行
翌年宝暦13年(1763年)には、平賀源内が記した「物類品隲」を刊行。
「物類品隲」は宝暦7年(1757年)から宝暦12年(1762)年にかけて5回行われた薬品会の出品解説書。
2000を超える出品物の中から360品を厳選して解説し、その中でも特に珍しい32品を絵と共に紹介しています。
また、朝鮮人参の栽培方法やさとうきびを用いた砂糖の製法も紹介。
今を生きる私達が見ても楽しめる本です。
杉田玄白・前野良沢著「解体新書」を刊行
安永3年(1774年)、杉田玄白が清書係を、前野良沢が翻訳係を務めた「解体新書」を刊行します。
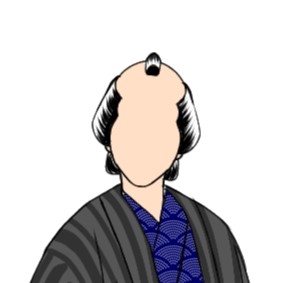
ご存知のとおり…
「解体新書」は西洋医学書「ターヘル・アナトミア」を日本語に翻訳した書物。
須原屋市兵衛が「解体新書」を刊行する4年前の明和8年(1771年)。
蘭方医・杉田玄白、前野良沢は小塚原刑場で罪人の解剖を見学しました。
この時、杉田玄白と前野良沢は所持していた「ターヘル・アナトミア」と解剖を見比べます。
そして、内容の正確さに驚きました。
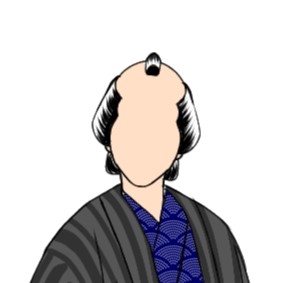
「この本は日本の医学を発展させるに違いない」
そう確信した杉田玄白と前野良沢は「ターヘル・アナトミア」を日本語に翻訳することに決めました。
もちろん、オランダ語の辞書はありません。
オランダ語を読めない二人は2年の歳月をかけて、「ターヘル・アナトミア」を翻訳します。
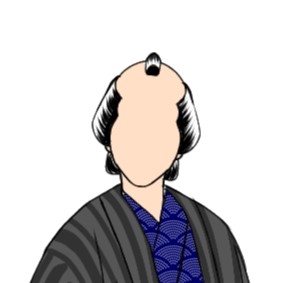
こうして「解体新書」が完成しましたが、当時の医学は漢方医学が主流。
西洋医学は世に受け入れられないおそれがありました。
また、解体新書の出版が幕府に認められない、弾圧されるおそれもありました。
そこで、杉田玄白の友人で江戸幕府の奥医師・桂川甫三を通じて、第10代将軍・徳川家治に献上。
須原屋市兵衛の「解体新書」の刊行により、
☑ 日本における医学を発展させ
☑ オランダ語の理解が進み、西洋の書物を次々と翻訳する
ことができました。
林子平著「三国通覧図説」を刊行
寛政4年(1792年)、林子平の記した「三国通覧図説」を刊行します。
ところが、「三国通覧図説」は幕府に咎められ絶版となってしまいました。
また、版元である須原屋市兵衛自身も重過料に課されました。

文化3年(1806年)には、文化の大火で被災。
蔵を持っていなかった須原屋市兵衛は経済的に大打撃を受けます。
文政6年(1823年)に休業
・文化4年(1807年)に「由利稚野居鷹」
・翌年文化5年(1808年)に「三七全伝南柯夢」
と、たて続けに曲亭馬琴(滝沢馬琴)の作品を刊行。

ただ、以降単独出版は途絶えます。
文化8年(1811年)に二代目・須原屋市兵衛宗和が亡くなると、共同出版のみを手がけるようになりました。
文政年間(1818年から1831年)には、経営が総本家である須原屋茂兵衛に委ねられます。
三代目・須原屋市兵衛和文が文政6年(1823年)に亡くなると、ついに休業に入りました。
須原屋市兵衛が「三国通覧図説」で処罰された理由
紹介したように、「三国通覧図説」は幕府に咎められ絶版、須原屋市兵衛も処罰されることになりました。
「三国通覧図説」は天明5年(1785年)に林子平が書いた地理書です。
日本に隣接する三国・朝鮮、琉球、蝦夷とその他の島々の風俗を挿絵入りで解説しています。
また、三国通覧輿地路程全図、琉球全図、無人島之図、朝鮮国全図、蝦夷国全図の地図が付いています。
といっても、本州、四国、九州以外の地域を測量するのは困難。
そのため、地図は正確さを欠いた内容となっています。

ただ、林子平が書きたかったことは、日本を取り巻く近隣国について。
近い将来、日本が外国から受ける圧力を予感して書いていたんです。
ただ、これでは、「三国通覧図説」が幕府に咎められた理由は分かりませんよね。
実は「三国通覧図説」そのものが幕府に咎められたわけではありません。
同じく林子平が書いた「海国兵談」が咎められたんです。
内容は外国から日本を守るための軍備の必要性を説くものでした。
松平定信に疎まれ、発行を禁止され、また、版木没収の処分となりました。
19世紀に入ると、
☑ 江戸湾の防衛政策に採用される
☑ 富国強兵論に大きな影響を与える
など、高く評価されます。

ただ、刊行した当時は「幕府の軍事体制を批判している」と受け止められたんです。
「海国兵談」の著書・林子平の 「三国通覧図説」は幕府から警戒され、版元である須原屋市兵衛も処罰されることになったんですね。
まとめ:須原屋市兵衛は処罰を恐れなかった学者の版元!
須原屋市兵衛の生涯、「三国通覧図説」で処罰された理由を紹介しました。
須原屋市兵衛は版元であり、歴代店主の通称。
江戸の出版業界最大手といわれる須原屋茂兵衛から暖簾分けしました。
平賀源内、杉田玄白や前野良沢、林子平らなどの学者の書物を手がけ、独自路線を貫いた須原屋市兵衛。
須原屋茂兵衛は書物問屋の代表だったんですね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()