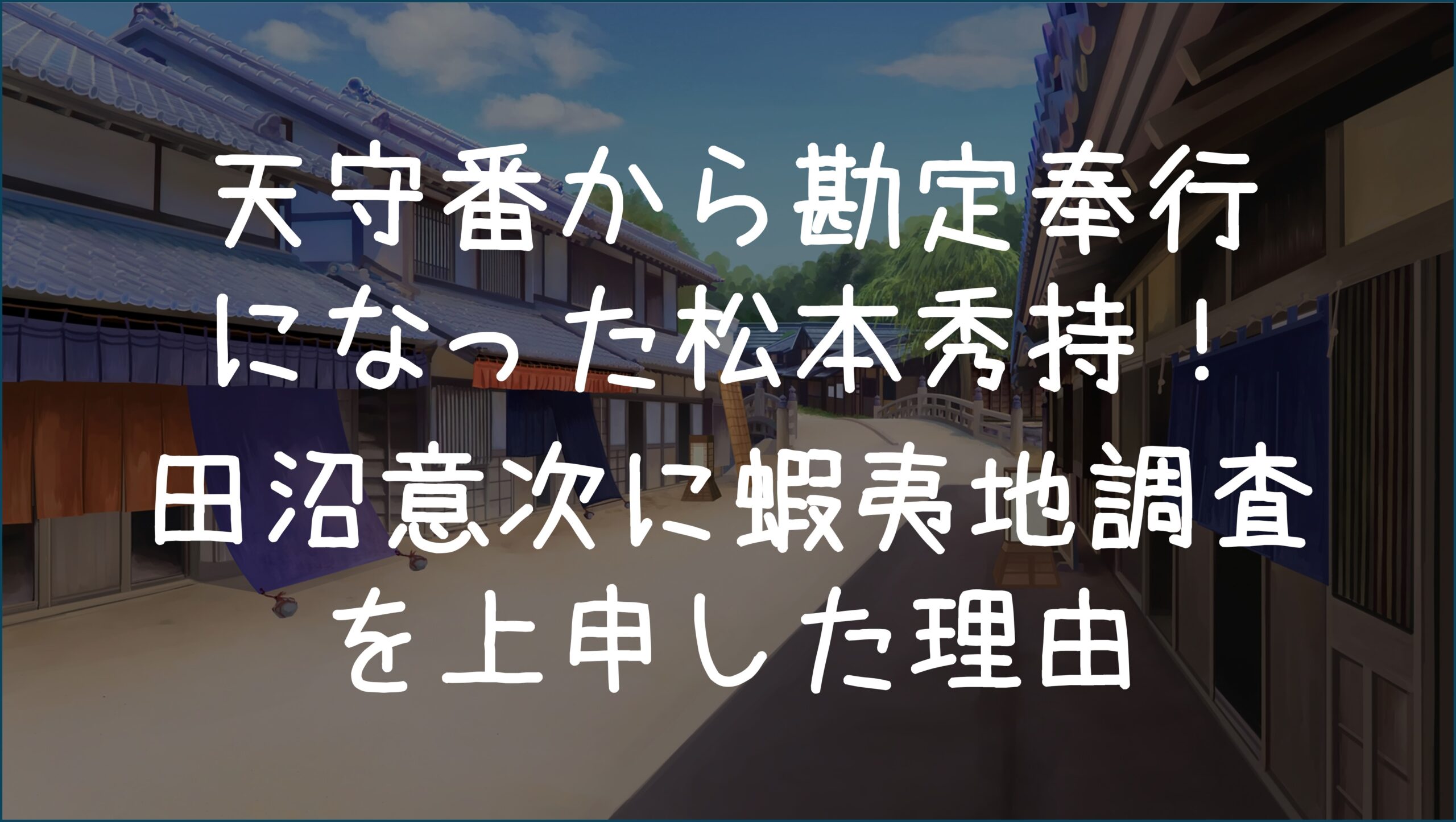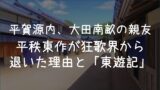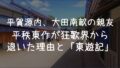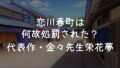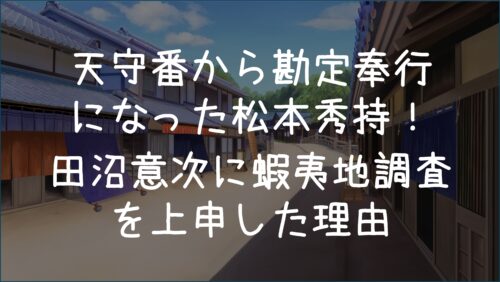
徳川家重・家治の2代に仕え、老中として田沼時代を築いた田沼意次。
田沼意次の腹心であり、ブレーン的存在だったのが松本秀持です。
松本秀持の生涯、田沼意次に蝦夷地調査を上申した理由を紹介します。
天守番から勘定奉行になった松本秀持の生涯
松本秀持は享保15年(1730年)生まれで、松本忠重の子として誕生しました。
松本家は代々天守番を務めていました。
 (江戸城富士見櫓。天守焼失後は天守の代わりに利用されました)
(江戸城富士見櫓。天守焼失後は天守の代わりに利用されました)
本来天守番は江戸城の天守を守る役職。
江戸幕府が成立して間もない頃、天守番は大番より高い地位にありました。
ただ、明暦3年(1657年)に明暦の大火が起こり、江戸城五重の天守は焼け落ちてしまいます。
天守番は天守を守る必要がなくなりますが、役職名だけは残されました。

明暦の大火をきっかけに、天守番は名ばかりの役職になっていたんです。
代々天守番を務める家に誕生した松本秀持は身分の低い家柄出身でした。
勘定奉行に抜擢される
身分の低い家柄の出身であっても、才能のある人はもちろんいます。
松本秀持もその一人で、老中・田沼意次の目に留まり、勘定方に抜擢されます。
明和3年(1766年)には、勘定組頭、後に勘定吟味役となります。
安永8年(1779年)には、勘定奉行に任命され、500石の知行を受けました。
田安家の家老を兼務する
天明2年(1782年)から、御三卿の一つである田安家の家老を兼務します。
 (旧江戸城田安門。田安門の南西に田安家がありました)
(旧江戸城田安門。田安門の南西に田安家がありました)
田安徳川家の第2代当主・徳川治察は安永3年(1774)に亡くなりました。
徳川治察に妻子がいなかったため、田安家の当主は不在になります。
天明7年(1787年)に第11代将軍・徳川家斉の弟・斉匡が継ぐまでの13年間当主不在の状態が続きました。
この13年の間に任命された家老は勘定奉行から選出されました。
印旛沼、手賀沼の干拓事業を進める
印旛沼と手賀沼は千葉県北部にある利根川水系の湖沼です。
文禄3年(1594年)から、江戸を利根川の氾濫による水害から守るため、利根川東遷事業が行われました。
これにより、印旛沼と手賀沼は利根川の下流となり、周辺に住む人々は水害を受けるようになりました。
そこで、松本秀持が中心となって、
・印旛沼と手賀沼の水を江戸湾(現在の東京湾)に流すための掘割工事
・江戸の人々の食料を生産するための干拓事業
を進めました。
蝦夷地に調査団を派遣する
天明4年(1784年)田沼意次から蝦夷地調査を任された松本秀持は、
① 第一次調査では、狂歌師・平秩東作、元オランダ通詞・荒井庄十郎
② 第二次調査では、普請役・青島政教、煙草屋・最上徳内
らを派遣しました。
平秩東作の「東遊記」は、当時の蝦夷地を知る貴重な資料として、現在でも高く評価されています。
68歳で亡くなる
二度の蝦夷地調査を経て、いよいよ蝦夷地の開発に乗り出そうとします。
でも、天明6年(1786年)に、田沼意次が失脚し、蝦夷地の開発は中止になります。
田沼意次と親しくしていた松本秀持も小普請に落とされ、自宅から出ることを禁止されました。

また、天明7年(1787年)、勘定組頭・土山宗次郎が越後買米事件で処刑されます。
連帯責任を問われた松本秀持は知行を減らされました。
天明8年(1788年)に自宅から出ることを許されます。
でも、政界に戻ることはなく、寛政9年(1797年)に68歳で亡くなりました。
松本秀持が田沼意次に蝦夷地調査を上申した理由
紹介したように、松本秀持は田沼意次から蝦夷地調査を任されました。
実は、松本秀持が田沼意次に蝦夷地調査を上申したんです。
田沼意次が蝦夷地調査を命令したのは、その必要性を感じたから。
それは、仙台藩の藩医・工藤平助の「赤蝦夷風説考」を読んで、蝦夷地開拓の必要性を感じたからです。
明和3年(1766年)、ロシア人がカムチャツカ半島から南下し、得撫島を脅かします。
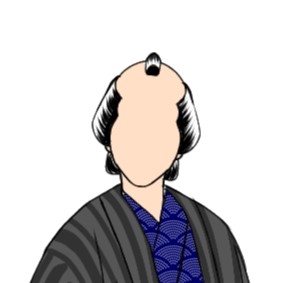
得撫島(ウルップ島)は千島列島にある島です。
正徳5年(1715年)松前藩主は幕府に、千島列島は松前藩領だと報告していました。
安永7年(1778年)には、ロシア商人がノッカマフ(根室半島)に上陸し交易を求めました。
社交性のあった工藤平助は、
・松前の知人から、ロシアの脅威
・長崎の知人から、ロシアが南下する目的
を耳にしました。
もちろん、幕府もロシアが南下していることは把握していたと思います。
ただ、工藤平助が把握している情報以上のことは把握していませんでした。
日本は清(中国)に対して、蝦夷地産の煎海鼠や干鮑を売って交易していました。
幕府にとって大きな財源であった蝦夷地。
もし、蝦夷地がロシアに攻撃されたら、財源を確保するどころか、日本が侵略されてしまう。
この事態を受けて、天明3年(1783年)、仙台藩の藩医・工藤平助は「赤蝦夷風説考」を書いたんです。
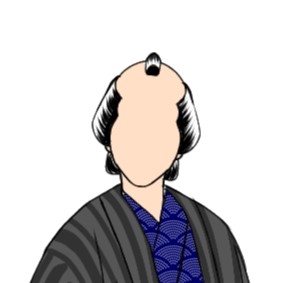
松本秀持は「赤蝦夷風説考」を読んで、
・蝦夷地を開拓して、産物を今以上に確保し、充実した交易をしなければいけない
・ロシアによる日本侵略を防がなければいけない
と感じ、蝦夷地調査を上申したんですね。
まとめ:松本秀持は田沼意次の功績に大きく関わっていた!
松本秀持の生涯、田沼意次に蝦夷地調査を上申した理由を紹介しました。
身分の低い家柄出身でありながら、田沼意次に才能を見出された松本秀持。
松本秀持は「赤蝦夷風説考」を読んで、交易の充実化とロシアの日本侵略防止の必要性を感じ、蝦夷地調査を進めました。
太平の世を生きながらも、将来日本を襲う脅威に備えようとした松本秀持。
田沼意次の抜擢する理由がよく分かりますね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()