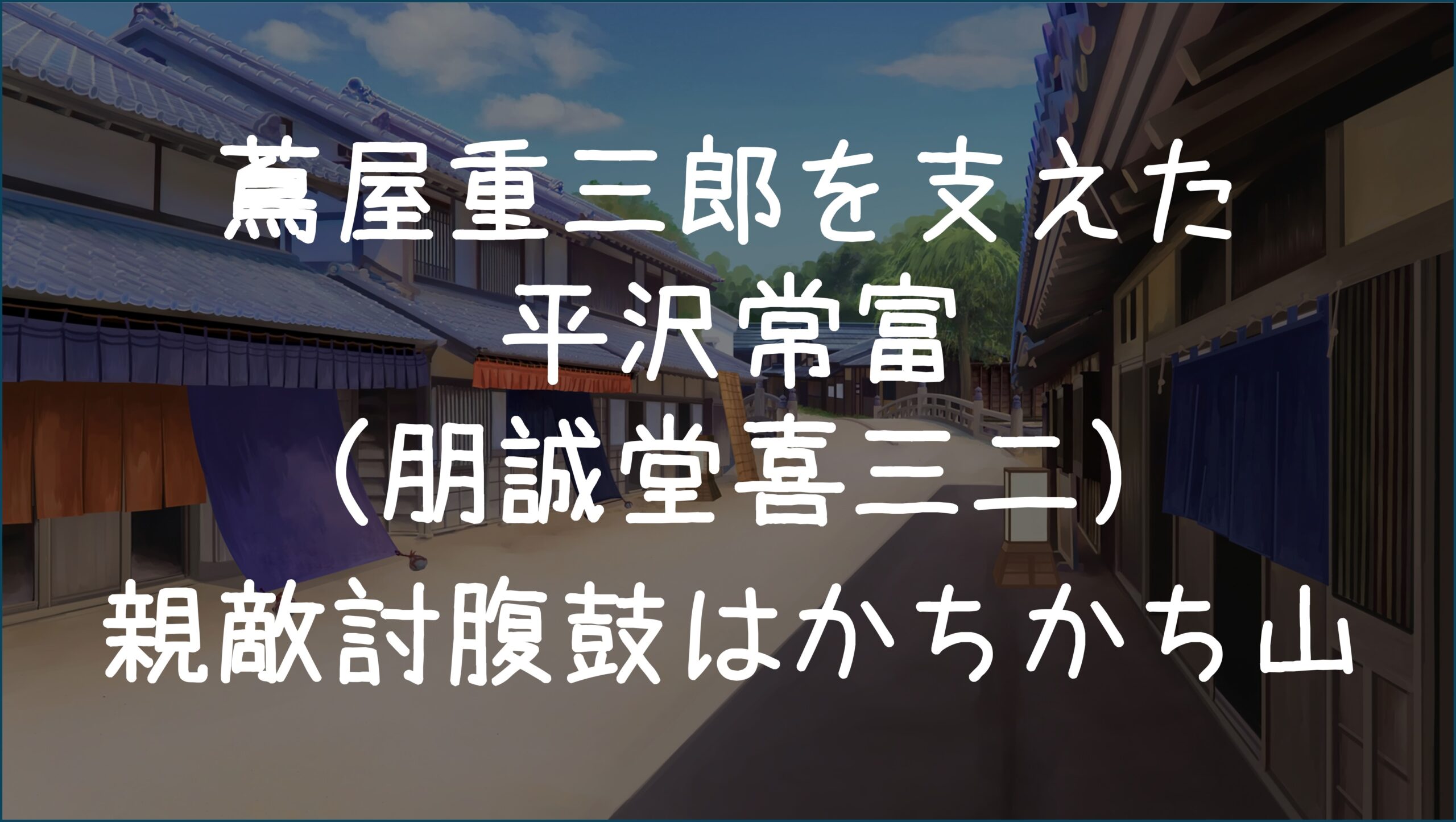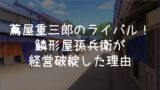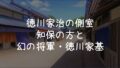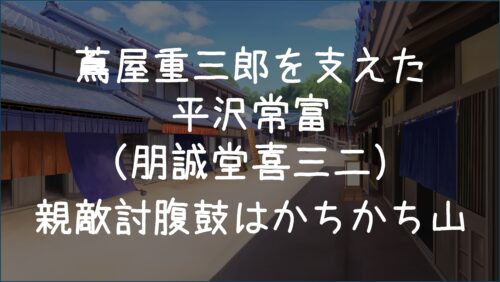
安永4年(1775年)に不祥事を起こした鱗形屋孫兵衛。
大人気の版元になるチャンスが蔦屋重三郎に巡ってきました。
この時、蔦屋重三郎を支えたのが平沢常富です。
平沢常富(朋誠堂喜三二)の生涯、黄表紙「親敵討腹鼓」を紹介します。
平沢常富(朋誠堂喜三二)ってどんな人?
平沢常富は享保20年(1735年)生まれ。
江戸の武士・西村久義の三男として誕生しました。
14歳で母方の親戚にあたる久保田藩士・平沢家の養子になります。

この時、西村から平沢に改姓したんですね。
江戸留守居役になる
幼少期から俳諧や漢学を学んで教養を身につけてきた平沢常富。
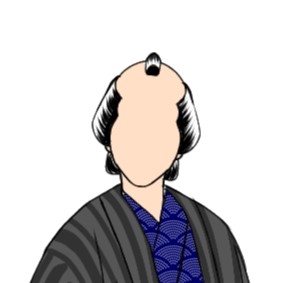
久保田藩の江戸留守居役筆頭となり、
・江戸藩邸を取り仕切る
・幕府や他の藩との交渉を行う
など、現在でいう外交官のような仕事をしました。
江戸留守居役は藩の中でも120万石の高給取り。
平沢常富が政治的才能を兼ね備えていたことがわかります。
「当世風俗通」を刊行し、一躍有名作家に
宝暦年間(1751年から1764年)、自ら「宝暦の色男」と称して吉原に通い続けます。
安永2年(1773年)、洒落本「当世風俗通」を刊行し、一躍有名作家となりました。
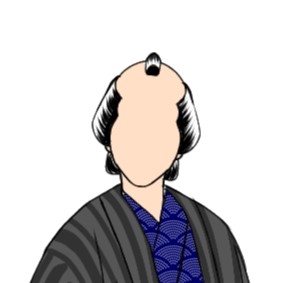
「当世風俗通」は現在でいうメンズファッション雑誌。
流行のヘアスタイルやファッションアイテムを紹介しています。
作者は金錦佐恵流ですが、これは平沢常富の別名だといわれています。
「文武二道万石通」が咎められ、黄表紙から手を引く
仕事との合間を縫って、朋誠堂喜三二として黄表紙を執筆。
天明8年(1788年)、黄表紙「文武二道万石通」を刊行しました。
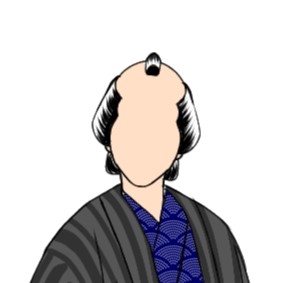
「文武二道万石通」の主人公は、源頼朝と御家人の畠山重忠。
ところが、
・江戸幕府第11代将軍・徳川家斉と老中・松平定信に似ている
・寛政の改革を風刺している
と判断され、久保田藩第9代藩主・佐竹義和から咎められます。
江戸留守居役という高い役職に就いていても、主君に逆らうことはできません。
以降、平沢常富は黄表紙から手を引くことになりました。
78歳で亡くなる
黄表紙から手を引いた平沢常富は「手柄岡持」という狂名で狂歌を作ります。
享和3年(1803年)、68歳で「後はむかし物語」という随筆を刊行。
文化10年(1813年)、78歳で亡くなりました。
平沢常富(朋誠堂喜三二)は蔦屋重三郎を支えた?
紹介したように、鱗形屋孫兵衛は安永4年(1775年)に不祥事を起こしました。
翌年には吉原細見を刊行したものの、市場は既に蔦屋重三郎の独占状態。
そこで、安永6年(1777年)。
鱗形屋孫兵衛は平沢常富の黄表紙「親敵討腹鞁」を出版し、巻き返しを図ります。
ただ、平沢常富は吉原に通い詰めるうちに、蔦屋重三郎と親しくなっていました。
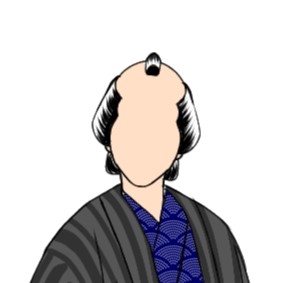
やがて、吉原を盛り上げようとする蔦屋重三郎の想いに共感。
「親敵討腹鞁」を出版した年と同じ安永6年(1777年)。
蔦屋重三郎を版元として、「娼妃地理記」を出版します。
以降、蔦屋重三郎の主力商品である「吉原細見」の序文を担当しました。

平沢常富は鱗形屋孫兵衛ではなく、蔦屋重三郎を応援したんです。
蔦屋重三郎のもとでヒット作を次々と出版し、蔦屋重三郎を大人気の版元に押し上げました。
親敵討腹鼓はかちかち山?
安永6年(1777年)に出版した黄表紙「親敵討腹鼓」。
実はかちかち山の後日譚といわれています。
まずは、かちかち山のあらすじをおさらい。
狸に妻(おばあさん)を殺されたおじいさん。
ウサギは狸が背負う薪に火をつけ、おじいさんに代わって復讐しました。
かちかち山は室町時代に作られた話だと考えられています。
対して、平沢常富の「親敵討腹鞁」は次のような話です。
子狸(殺された狸の子供)は親の敵を討とうと、ウサギに接触し、切腹に追い込みます。後日、子狸は猟師を利用して狐を殺しました。
すると、子狐(殺された狐の子供)は子狸と猟師に接触し、親の敵を討ちました。
まるで堂々巡りの親の敵討ちですね。
まとめ:吉原が平沢常富と蔦屋重三郎を繋いだ!
平沢常富(朋誠堂喜三二)の生涯、黄表紙「親敵討腹鼓」を紹介しました。
江戸留守居役でありながら、自ら「宝暦の色男」と称した平沢常富。
平沢常富が粋で人情に厚かったからこそ、蔦屋重三郎と仲良くなれたのかもしれませんね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()