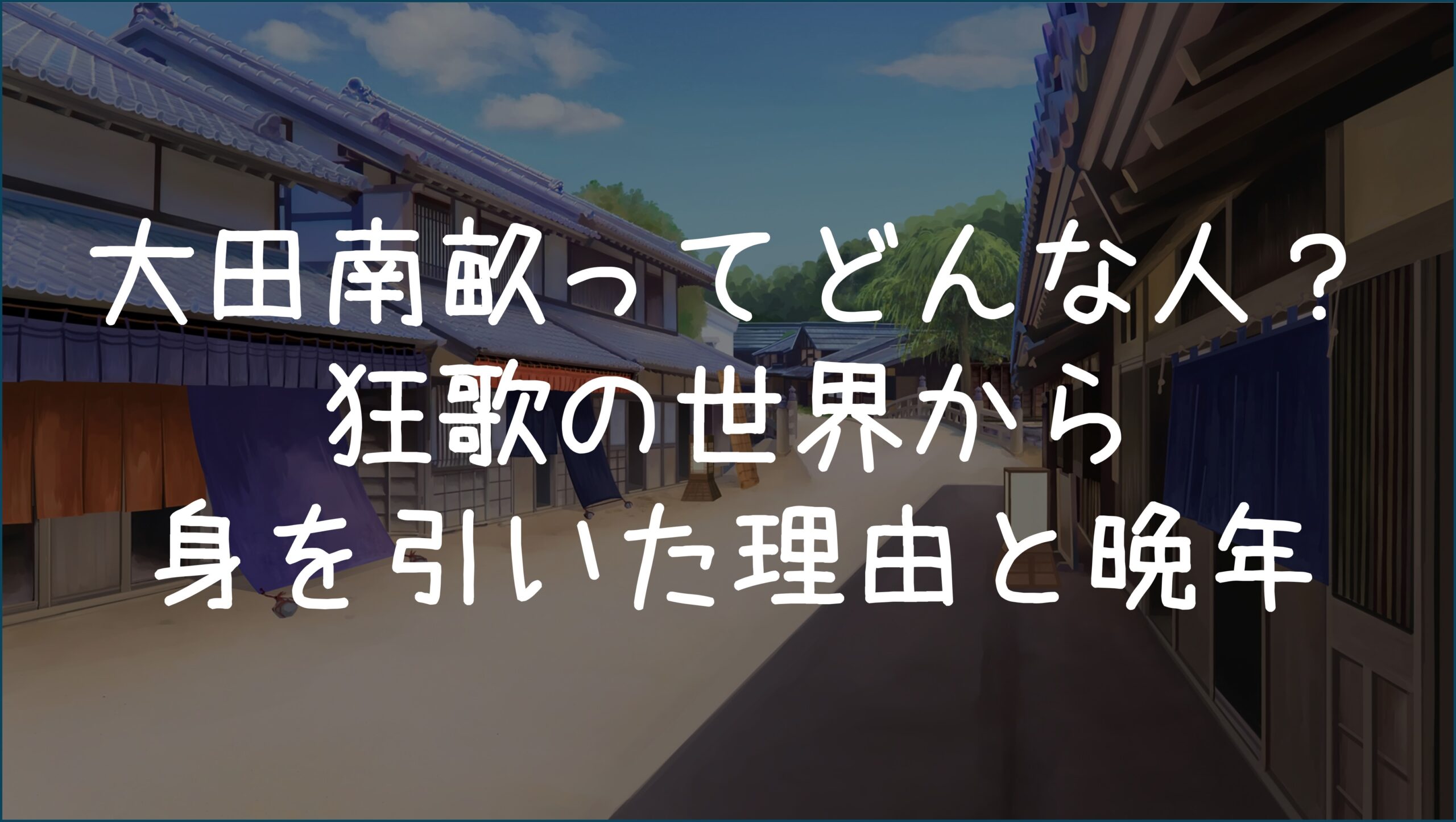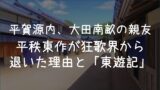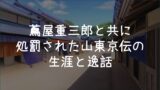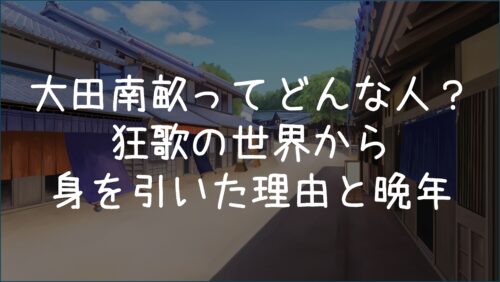
ある時は四方赤良、ある時は寝惚先生、そして、ある時は蜀山人。
文学のさまざまな分野で才能を発揮した大田南畝。
ところが、天明7年(1787年)には狂歌の世界から身を引きます。
大田南畝の生涯、狂歌の世界から身を引いた理由と晩年を紹介します。
大田南畝ってどんな人?
大田南畝は寛延2年(1749年)生まれ。
御徒を務める父・大田正智(吉左衛門)と母・利世の間に誕生しました。
混乱を避けるため、こちらでは大田南畝と記載します。
御徒とは「徒士」とも呼ばれ、歩いて参戦する武士を指します。
大田南畝はいわゆる下級武士の家庭に生まれたんですね。
「明詩擢材」5巻を刊行する
大田南畝は貧しい幼少期を送りますが、学問や文筆が得意でした。
子供に学びの場を与えたいと思った大田正智は札差(米の仲介業者)からお金を借ります。
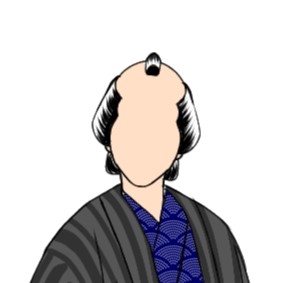
次回支給される蔵米の売却を依頼する
と札差に約束して、借金していたんです。
大田南畝は15歳で江戸六歌仙の一人・内山椿軒に入門し、国学や漢学、漢詩や狂詩などを学びました。
17歳で父と同じ御徒の見習いになりますが、時間をなんとか作って学問を続けました。
明和3年(1766年)には、漢詩を作るのに知っておきたい用語辞典「明詩擢材」5巻を刊行しました。
「寝惚先生文集」を刊行する
仕事を始めても学問を続けてきた大田南畝。
明和4年(1767年)、これまで書きためた狂歌が狂歌師・平秩東作から高く評価されます。
そして、漢詩のパロディ・狂詩集「寝惚先生文集」を刊行。
当時漢詩が流行していたため、「寝惚先生文集」は大人気を博します。
こうして、大田南畝は狂歌師として一躍有名になりました。
四方赤良と称して狂歌会を自ら開催する
明和6年(1769年)、狂歌師・唐衣橘洲の歌会に参加。
以降、「四方赤良(よものあから)」と称して、狂歌会を自ら開催します。
① 大田南畝(四方赤良)
② 唐衣橘洲(小島橘洲)
③ 朱楽菅江(山崎景貫)
は狂歌三大家と呼ばれ、江戸でさまざまな文化人が狂名を称して狂歌を楽しむきっかけをつくりました。
安永5年(1776年)、落合村(現在の東京都新宿区)で観月会を開きます。
安永8年(1779年)には、高田馬場の茶屋「信濃屋」で70人以上を集めて、5夜連続で観月会を開きました。
黄表紙「嘘言八百万八伝」を出版する
翌年の安永9年(1780年)、版元・蔦屋重三郎のもとで黄表紙「嘘言八百万八伝」を出版。
嘘やホラが得意な万八という人物の話で、狂歌を中心に書いてきた大田南畝はこれまでとは異なる作風で才能を発揮しました。
天明3年(1783年)、朱楽菅江と共に「万載狂歌集」を編集します。

「万載狂歌集」は平安時代末期に編纂された勅撰和歌集「千載和歌集」のパロディ。
大田南畝は勘定組頭・土山宗次郎から経済的援助を得て、吉原に通うようになりました。
天明6年(1786年)、吉原の松葉屋の遊女・三保崎を身請けし、妾として自宅に迎えました。
狂歌の世界から身を引いた理由
天明7年(1787年)、松平定信による寛政の改革が始まります。
大田南畝に経済的支援をしていた土山宗次郎の横領が発覚し、土山宗次郎は斬首されてしまいました。
更に、風紀の取り締まりが厳しくなります。
「嘘言八百万八伝」の版元・蔦屋重三郎や親交の深かった山東京伝も処罰されていまいました。
斬首された土山宗次郎や処罰された蔦屋重三郎、山東京伝と関係のあった大田南畝も目を付けられていました。
これを機に、大田南畝は狂歌の世界から身を引きます。
幕臣として仕事に励みながら、随筆などを執筆するようになりました。
天明7年(1787年)には、横井也有の俳文集「鶉衣」を編纂、出版します。

寛政4年(1792年)、旗本や御家人、その子弟を対象とした、朱子学の試験「学問吟味登科済」がスタート。
46歳で受験した大田南畝は甲科及第首席合格となります。

幕府から目を付けられていた大田南畝は出世を諦めていました。
でも、2年後の寛政8年(1796年)には、支配勘定に任命されました。
享和元年(1801年)、大坂の銅座に赴任。
江戸を離れた大田南畝は「蜀山人」の号で狂歌を再開します。
その後、江戸にもどった大田南畝は永代橋崩落事故を偶然目撃。
文化4年(1807年)、大田南畝はこの事故を自ら取材し、証言集「夢の憂橋」を出版しました。
晩年は?
文化9年(1812年)、長男・定吉が支配勘定見習に任命されます。
大田南畝は定吉が自分と同じ支配勘定に任命されたことを喜びました。
ところが間もなく、定吉は体調を崩して職を失ってしまいました。
大田家には、
・体調を崩して職を失った長男
・職に就いていない次男
・育ち盛りの孫
がいます。
次男と孫が独立するまでは稼がなければいけない。
大田南畝は隠居を諦めて働き続けました。
文政6年(1823年)、登城の道で転倒したことが原因で脳溢血を患い、大田南畝は75歳でこの世を去ります。
亡くなる直前、大田南畝は、
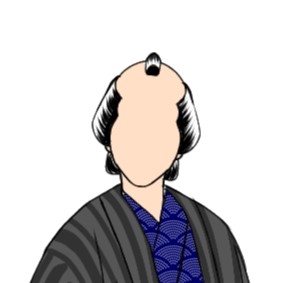
今までは人のことだと思ふたに俺が死ぬとはこいつはたまらん
という辞世の歌を残しました。
大田南畝の次男が仕官するまでの2年間生活費が与えられました。
まとめ:大田南畝は出自に左右されない努力家!
大田南畝の生涯、狂歌の世界から身を引いた理由と晩年を紹介しました。
下級武士の家庭に生まれながらも、学問と仕事に励んだ大田南畝。
平秩東作に才能を認められ、狂歌をはじめ、文学のさまざまな分野で活躍しました。
亡くなる直前に残した辞世の歌もまた大田南畝らしいですね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()