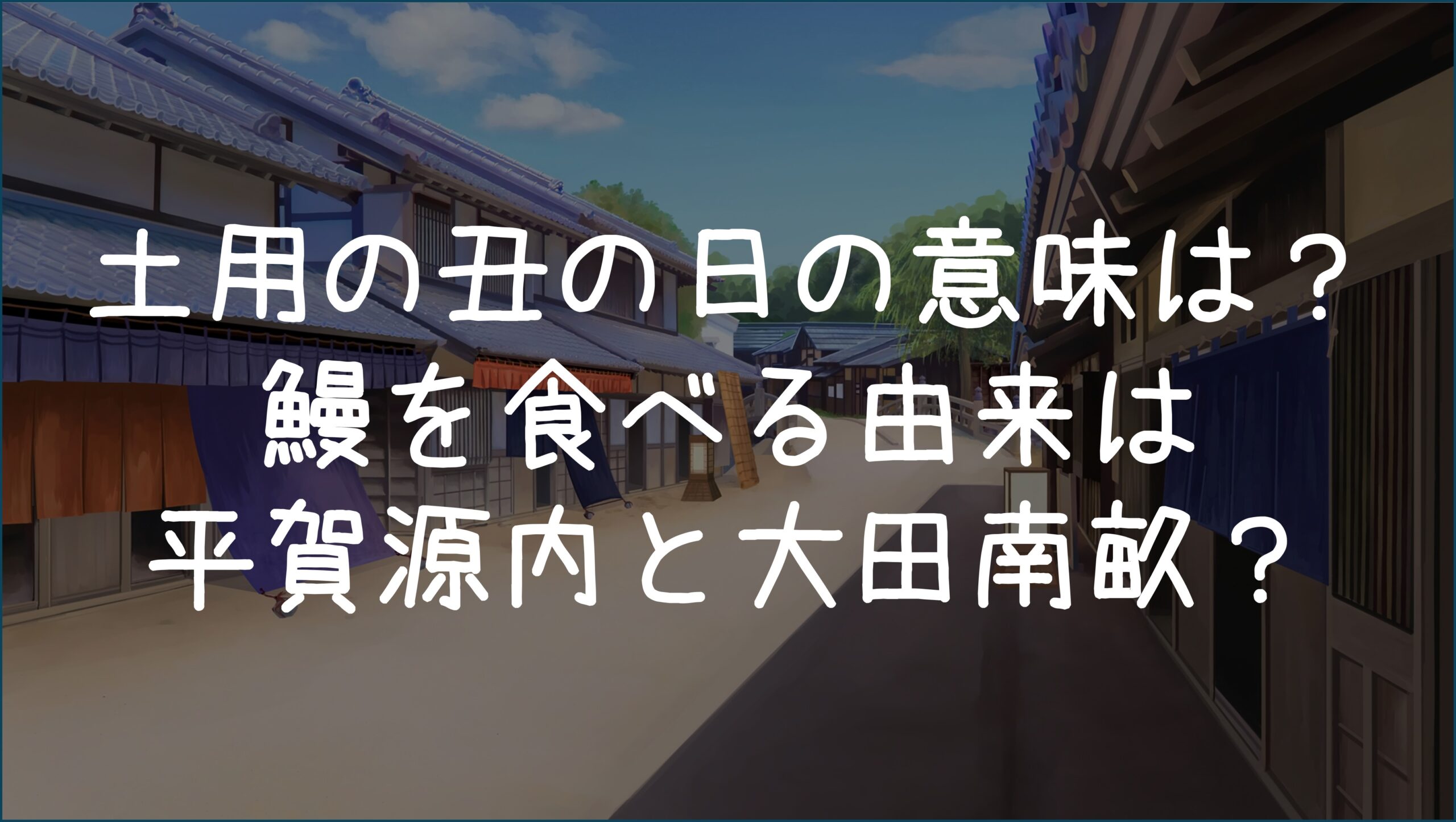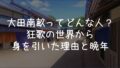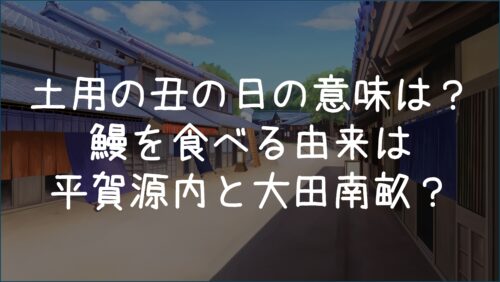
スーパーにずらりと鰻が並ぶ土用の丑の日。
鰻を普段買わない方も、
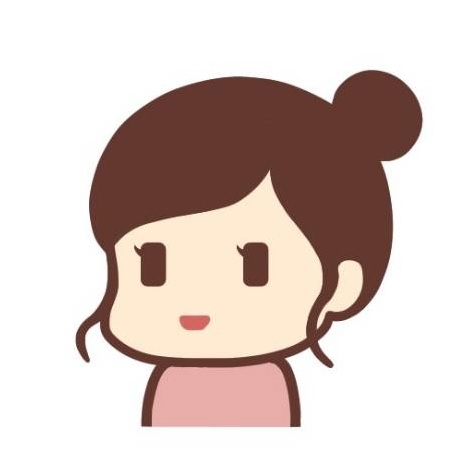
土用の丑の日ぐらいは…
と思って、買い物かごに入れる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
① 土用の丑の日の意味
② 鰻を食べる由来が平賀源内と大田南畝だといわれる理由
を紹介します。
土用の丑の日の意味は?
土用の丑の日は土用と丑の日の2つの単語から構成されています。
土用
土用とは、季節の変わり目とされる
・春土用(立春の直前18日間)
・夏土用(立夏の直前18日間)
・秋土用(立秋の直前18日間)
・冬土用(立冬の直前18日間)
を指します。
土用の間は土の神様が支配するといわれ、土を動かしてはいけない(土いじりをしてはいけない)とされています。
丑の日
丑の日とは、十二支で日にちを数えた時に、丑の日に該当する日を指し、12日に一度訪れます。
土用の丑の日に鰻を食べる由来は平賀源内と大田南畝?
土用の丑の日と聞くと、夏をイメージする方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
中には、
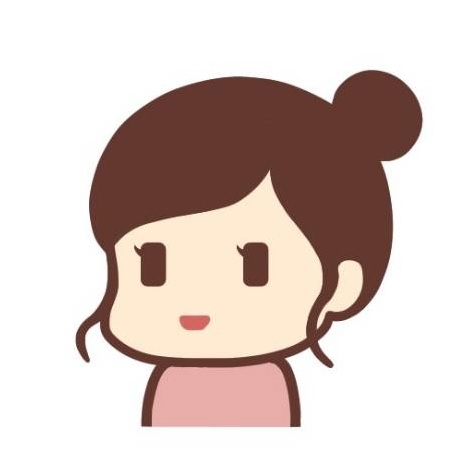
土用の丑の日は夏しかない!
と思い込んでいた方もいらっしゃると思います。
スーパーが夏に出すチラシに「土用の丑の日」と大きく目立つように掲載されるので無理もありません。
実は、土用の丑の日は一年に5回から7回程度あります。
奈良時代末期につくられた万葉集で、「暑い日は栄養価の高い鰻を食べて乗り切ろう」といった和歌が詠まれています。
この頃には既に、夏に鰻を食べることが奨励されていたんですね。

ただ、土用の丑の日の由来は、江戸時代に遡ります。
今でこそ鰻には養殖や外国産がありますが、当時は天然しかありません。
また、天然鰻の旬は秋から冬。
つまり、秋から冬にかけて、鰻を食べる人がほとんどでした。
ただ、旬ではない夏であっても、鰻は店頭に並びます。
鰻屋は「夏は鰻が売れなくて困る」とぼやきました。
由来は平賀源内?
鰻屋のぼやきを聞いた平賀源内は、
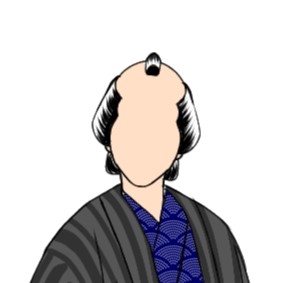
店頭に「本日丑の日」と書かれた張り紙をして宣伝してはどうか。
と提案しました。
日本では丑の日に「う」から始まる食べ物を食べると、
・縁起がいい
・夏の暑さに負けない
とされてきました。

「う」がつく食べ物を食べると、無病息災が叶うというのです。
「う」から始まる鰻は丑の日に食べるにはピッタリ。
平賀源内のアイデアにより、鰻屋は大盛況。
同じように鰻が売れなかった店は当然真似をします。
こうして、日本全国で「夏の土用の丑の日には鰻を食べる」という風習が生まれました。
由来は大田南畝?
平賀源内に同じく、鰻屋のぼやきを聞いた大田南畝。
大田南畝は「丑の日に鰻を食べると身体にいい」といった狂歌を詠んだとされています。
また、大田南畝の作品集「紅梅集」には、鰻屋「高橋」を詠んだ狂歌・狂詩が掲載されています。
まとめ:土用の丑の日に鰻を食べているとしたら…
① 土用の丑の日の意味
② 鰻を食べる由来が平賀源内と大田南畝だといわれる理由
を紹介しました。
実は一年間に5回から7回はある土用の丑の日。
夏の土用の丑の日に鰻を食べる風習は平賀源内と大田南畝が由来だといわれています。
200年以上の時を超えて、私達は二人の策略にはまっているのかもしれませんね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()