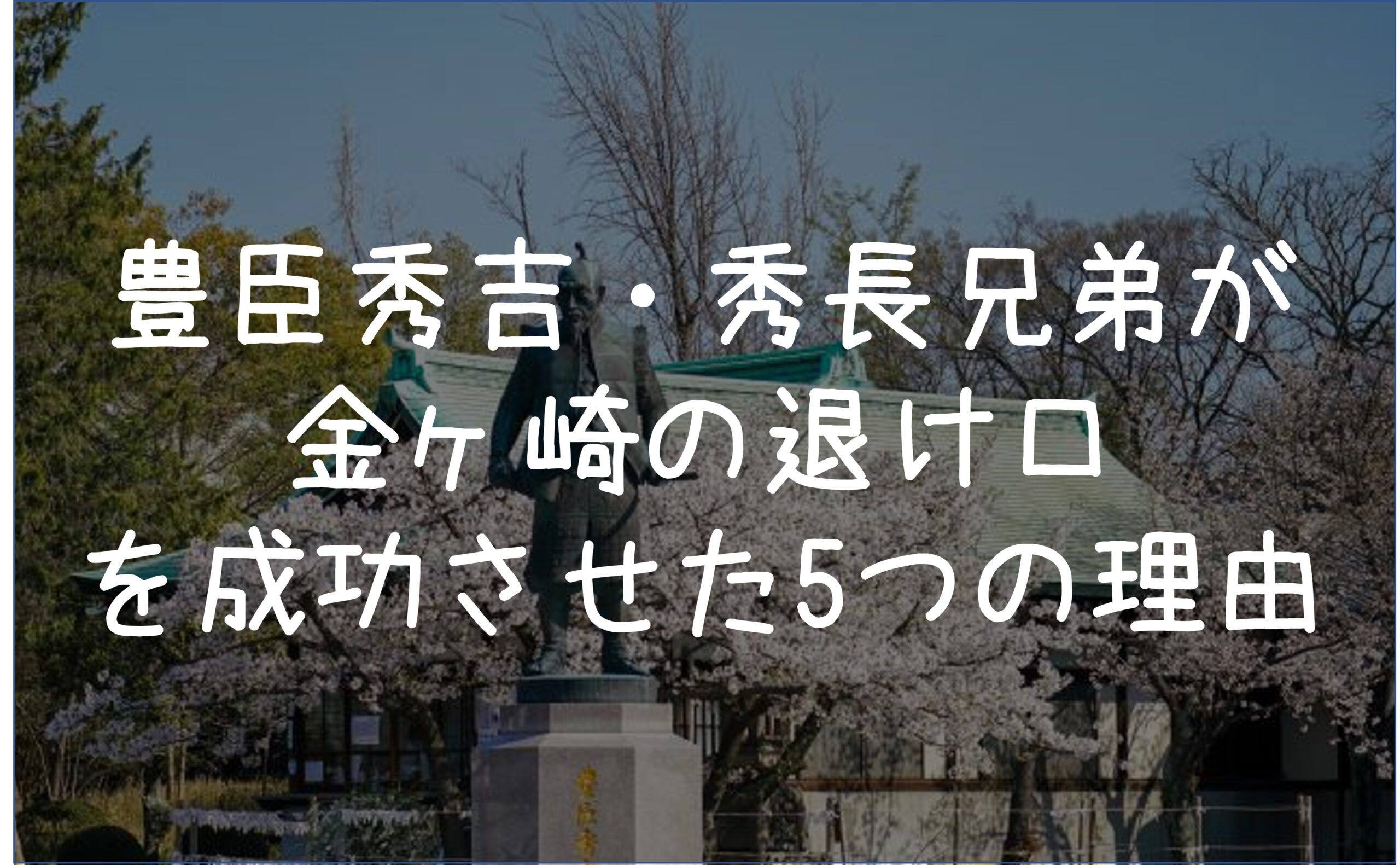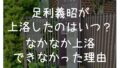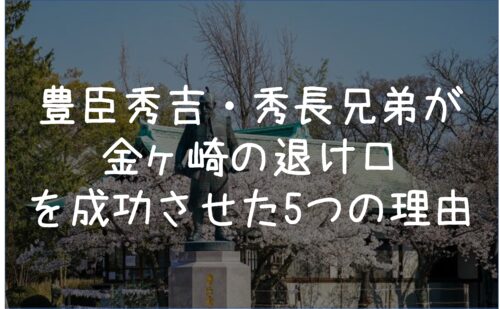
織田信長の大ピンチ・金ヶ崎の退け口。
殿(しんがり)を務め上げ、織田信長を大ピンチから救ったのは豊臣兄弟でした。
豊臣秀吉・秀長兄弟が金ヶ崎の退け口を成功させた5つの理由を紹介します。
金ヶ崎の退け口とは?
元亀元年(1570年)に、織田信長と朝倉義景の間に起きた金ヶ崎の戦い。

金ヶ崎の戦いは、織田信長が越前国に侵攻したことが始まりです。
金ヶ崎城主・朝倉景恒は無血開城し降伏。
織田信長は優勢に戦を進めていました。
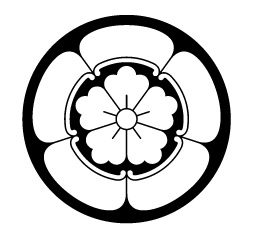
ところが、織田信長の義理の弟である浅井長政が裏切ったという情報が入ります。
浅井長政は北近江を治める戦国大名。
織田信長軍は朝倉義景(越前)・浅井長政(北近江)に挟み撃ちされる形となりました。
この危機的状況を察知した織田信長は撤退を決断。
ただ、織田信長に反感を抱く者は朝倉義景や浅井長政だけではありません。
湖西の小豪族や土民が反乱を起こす前に、織田信長は京まで駆け抜けなければいけませんでした。
金ヶ崎の退け口における殿
織田信長が無事京都にたどり着けるかどうか、カギを握るのが殿(しんがり)です。

殿の任務は敵の追撃を防ぎながら、本隊が安全に撤退できるよう時間を稼ぐこと。
戦国時代では、退却戦が最も多くの死者を出すといわれています。
戦いながら後退し、且つ、自軍の混乱を防ぐには、統率力、判断力、そして、冷静さが求められました。
この最も危険で困難な任務を自ら志願し引き受けたのが豊臣秀吉でした。

殿軍のリーダーには、さまざまな説があります。
例えば、
① 一色藤長の「武家雲箋」では、豊臣秀吉の他、明智光秀、池田勝正が殿を務めたとされています。
② 「信長公記」、「当代記」、「松平記」、「三河物語」では、豊臣秀吉の名前のみ記載されています。
③ 「寛永諸家系図伝」では、豊臣秀吉の配下・前野長康や生駒親正などの名前も記載されています。
豊臣秀吉が明智光秀や池田勝正を超えるようなリーダーであったかどうかは判りません。
ただ、豊臣秀吉が殿軍のリーダーであったことは間違いなさそうです。
豊臣秀吉・秀長兄弟が金ヶ崎の退け口を成功させた5つの理由
金ヶ崎の戦いには、織田信長の同盟相手である徳川家康軍も加わっていました。
織田信長が京にたどり着くまで、時間を稼ぐのが殿の役割。
ただ、織田信長が京にたどり着いたからといって、徳川家康軍を追い抜いて逃げるわけにはいきません。
さまざまな制約があった金ヶ崎の退け口。
豊臣秀吉・秀長兄弟はどのようにして成功させたのでしょうか。
少数部隊による伏兵
豊臣秀吉軍の兵は3000人。
金ヶ崎城は無血開城だったため、城郭はとても良い状態でした。
また、金ヶ崎周辺の山間部は大変狭く、視界が限られているため、伏兵や奇襲が成功しやすい地形でした。
豊臣秀吉は弟・秀長に700人の兵を預け、金ヶ崎城を守るように命令します。
一方、豊臣秀吉は城の四方に伏せました。
士気の維持
主君が無事撤退できるように時間を稼ぐ殿。
殿には敗北はあっても、勝利はなく、士気の上がる戦ではありません。
そこで、豊臣秀吉は「成功した暁には褒美をもらえる!」など声掛けをして、自軍の士気を維持しました。
混乱の抑制
誰か一人でも、
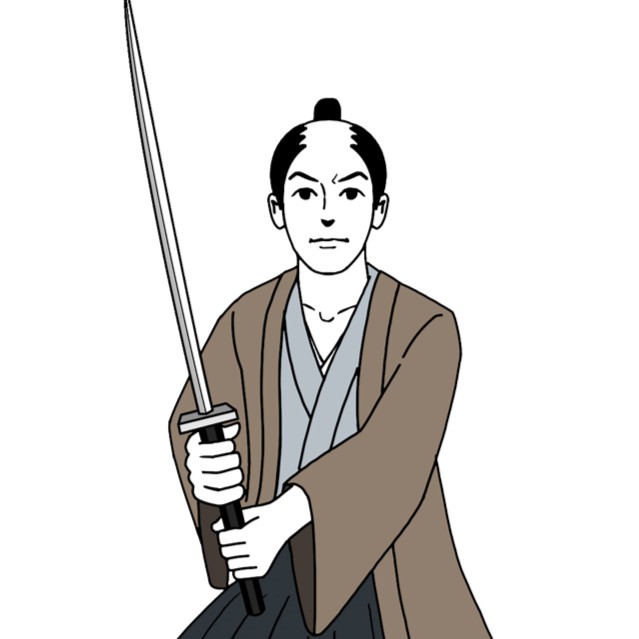
失敗するかもしれない…
死ぬかもしれない…
などのマイナス発言をすると、軍内で混乱が生じてしまいます。
一般的に戦国武将は血縁のある一族を家臣に加えていました。
でも、豊臣秀吉軍には弟・秀長を除いて一族がいません。
忠義の薄い兵は戦から逃げ出す可能性があります。
そこで、豊臣秀吉は忠義の厚い家臣に、部下を監視するよう命令しました。
偽装工作
金ヶ崎城を守る兵と城の四方に伏せる兵を合わせても、豊臣秀吉軍はたったの3000人。
20000人を超える朝倉・浅井連合軍に攻め込まれたら、すぐに敗北してしまいます。
そこで、豊臣秀吉は自軍の規模が大きく見えるように偽装工作をします。
撤退する織田軍から旗や幟を借りて、敵軍から見えるように立てました。
旗がいっぱい立っていると、3000人よりもはるかに多い兵が城に集まっているように見えます。
単純な偽装工作ですが、朝倉・浅井連合軍は戸惑い、すぐに攻撃をしかけてきませんでした。
豊臣秀長の補佐
伏兵、モチベーションの維持、混乱の抑制、偽装工作と、ここまで4つの成功理由を紹介しました。
軍にこの命令を下していたのは、もちろん豊臣秀吉です。
でも、兵が豊臣秀吉の無茶な命令に従うよう、豊臣秀吉と兵をサポートしたのは弟・豊臣秀長でした。
☑ 敵軍の状況を把握して兵の配置を整える
☑ 食料や休息の配分に努めて、兵の士気を保つ
☑ 部隊の先方と後方に指揮官を配置し、命令系統が途切れないように調整する
などしました。
冷静に指揮、補佐できる豊臣秀長がいたからこそ、豊臣秀吉は大胆な戦術を実行に移すことができました。
金ヶ崎の退け口を成功させたのは豊臣秀吉ですが、豊臣秀長がいたからこそ成功した策だったんですね。
まとめ:金ヶ崎の退け口は織田信長の信頼を得るチャンスだった!
豊臣秀吉・秀長兄弟が金ヶ崎の退け口を成功させた5つの理由を紹介しました。
義理の弟・浅井長政に裏切られ、危機的状況に陥った織田信長。
殿軍のリーダー・豊臣秀吉は兵を鼓舞。
豊臣秀長は兄・秀吉を補佐し、金ヶ崎の退け口を成功させました。
金ヶ崎の退け口は、織田信長が豊臣兄弟に注目するきっかけになったのではないでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()