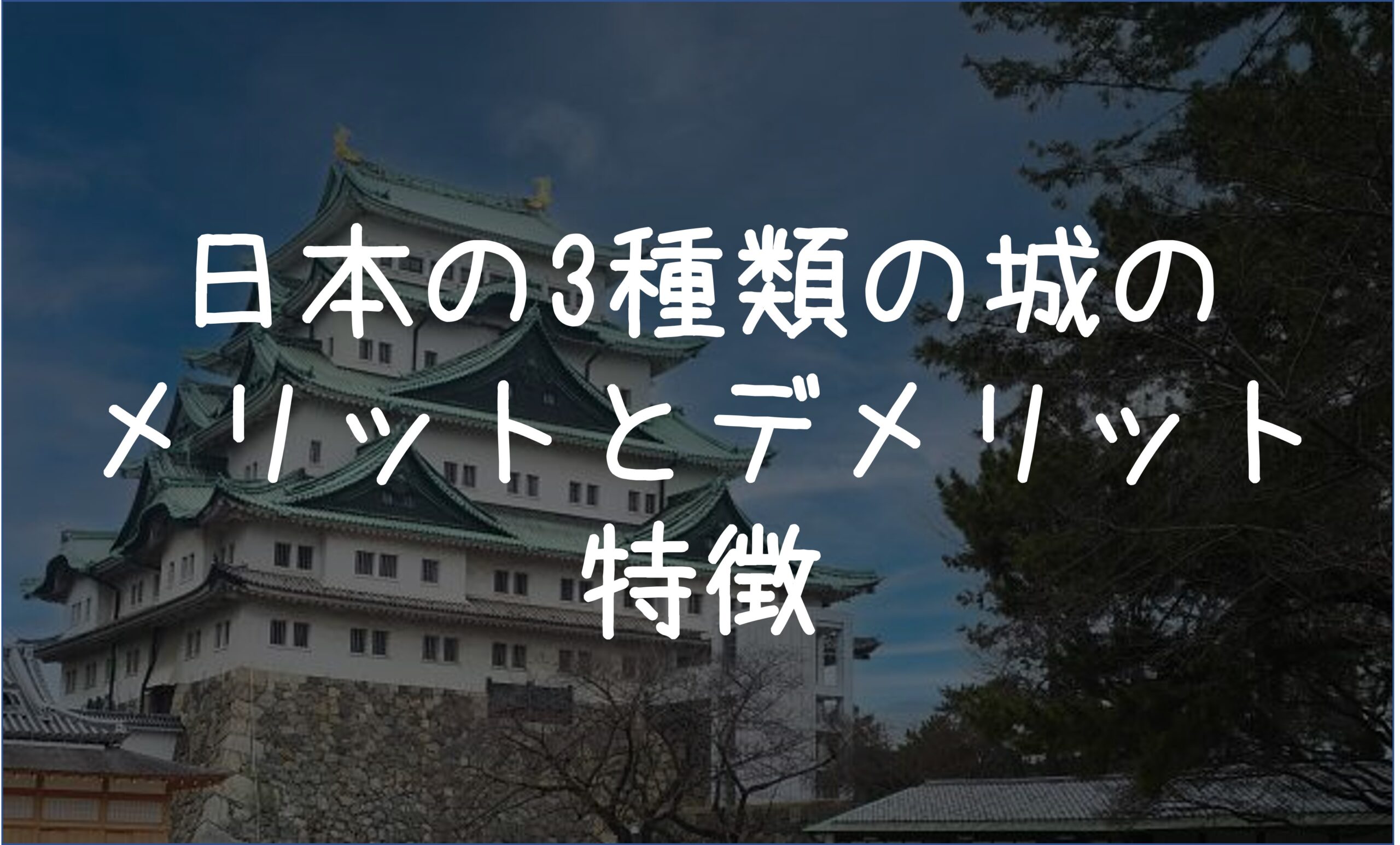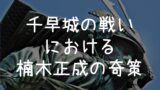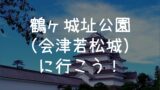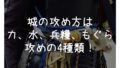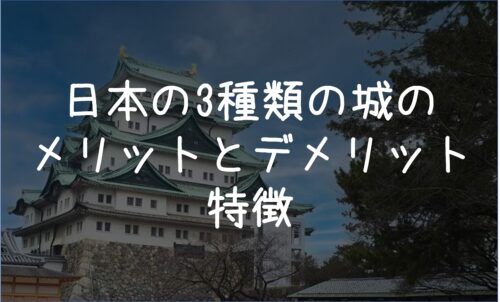
日本には昔、3万ほどの城があったといわれていますが、現在見学できる城は2000ほど。
これらの城は、立地によって3種類(山城、平山城、平城)に分けられます。
山城、平山城、平城のメリットとデメリット、特徴を紹介します。
山城のメリットとデメリット、特徴
山城は戦国時代の代表的な城です。
メリット
山城のメリットをみていきましょう。
時間をかけて、作戦を練られる
侵攻する敵軍や戦を見下ろすことのできる山城。
城から出ずに、敵軍の数や隊列、戦況を把握できたため、適切な作戦を練ることができました。
敵の侵攻を阻止できる
侵攻する敵軍はまず、山を登らなければいけません。
紹介したように、敵軍の数や隊列は城から丸見え。
敵軍が山を登っている間に、
・側道に兵を配備して攻撃する
・山頂と麓から挟み撃ちにする
などして、侵攻のスピードを緩めることができました。
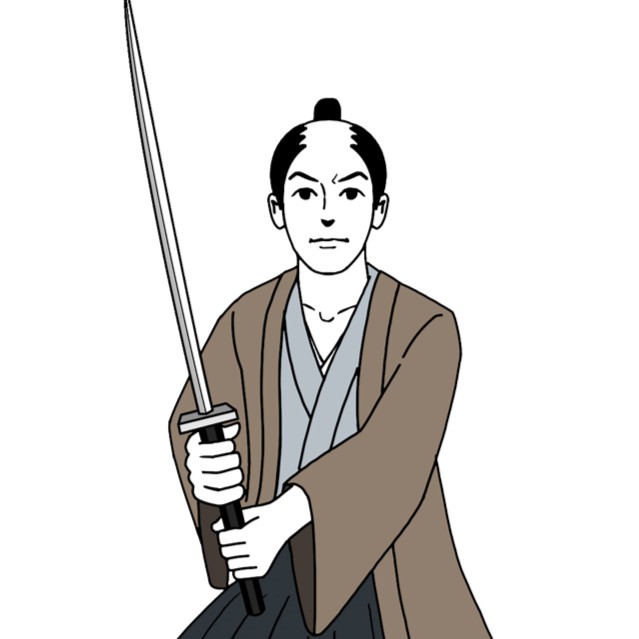
山城を攻撃するには、それなりの犠牲を覚悟しなければいけませんでした。
低コスト・短期間で築城できる
険しい山間部など、山の地形を利用して築いた山城。
難しい技術がいらないため、低コスト短期間で築城することができました。
デメリット
山城のデメリットをみていきましょう。
水の確保が困難
平野に比べて川の少ない山。
山城では水を確保することが難しく、麓から水を入れた甕を運んで貯水していました。
物資の搬入が大変
山城は日常生活を送る場所ではありません。
兵は普段、山の麓で暮らしていました。
城に長期滞在する場合、兵は食糧や日用品を持って山を登らなければいけませんでした。
山火事に弱い
紹介したように、山城は水の確保が困難。
敵軍が城に向かって火を放つと、消火活動は難航しました。
特徴
敵の動向に焦点をあてた山城は守りやすく攻めにくい城です。
デメリットを最小限に抑えるために、領主は山の麓に館を築くのが一般的でした。
 (千早城の本丸跡には千早神社があり、紅葉の名所になっている)
(千早城の本丸跡には千早神社があり、紅葉の名所になっている)
山城のルーツは、元弘2年(1332年)に楠木正成が金剛山の標高673メートルの位置に築いた千早城。
1000名の兵で、鎌倉幕府軍2万5000人を撤退させた千早城の戦いは、山城のメリットを活かした有名な戦です。
 (日本のマチュピチュ、天空の城と呼ばれる竹田城)
(日本のマチュピチュ、天空の城と呼ばれる竹田城)
その他、山城には次のような城があります。
① 春日山城
上杉謙信の父・長尾為景が標高約189メートルの春日山山頂に築いた春日山城。
天文17年(1548年)に上杉謙信が城主になりました。
② 岩村城
源頼朝の重臣である加藤景廉の長男・景朝(遠山景朝)が築いた岩村城。
標高約717メートルの城山に位置し、高取城、備中松山城と並んで日本三大山城の一つとされています。
③ 竹田城
山名宗全が標高約353.7メートルの古城山山頂に築いた竹田城。
天候によっては城が空に浮かんでいるように見え、人気の観光スポットになっています。
平山城のメリットとデメリット、特徴
平山城は小高い丘に築いた、山城と平城の特徴を合わせもった城です。
メリット
平山城のメリットをみていきましょう。
水の確保が楽
山城に比べて平坦な場所に築かれた平山城。
井戸を掘りやすく、水堀を設けやすいため、水を楽に確保することができました。
物資の搬入が楽
山の麓に城下町をつくったため、物資を容易に運搬することができました。
デメリット
平山城のデメリットは、高コスト・長期間で築城しなければいけないこと。
山城に比べて、平山城の築城にはコストと工事期間がかかりました。
特徴
山城に比べると劣る。
でも、(これから紹介する)平城に比べると勝る。
平山城は山城と平城のいいところどりをしたバランスの良い城です。
 (本能寺の変が起きて数日後に焼失した安土城)
(本能寺の変が起きて数日後に焼失した安土城)
平山城のルーツは、天正4年(1576年)に織田信長が標高199メートルの安土山山頂に築いた安土城。
織田信長は安土山の麓に広がる平野に城下町を作り、物資を楽に搬入できるようにしました。
山城には及ばない防御は、
・水を張った堀や何重もの曲輪
・家臣団の屋敷
などを設けて、守備力の増強を図ったといわれています。
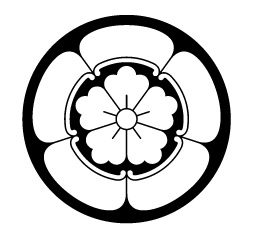
また、大規模な天守を設け、敵の動向を探ったり、権威を誇示したりしました。
安土城築城以降、城は戦に備えた砦であると同時に、権力を示す役割を担いました。
 (4階の展望室から房総半島や伊豆半島が一望できる小田原城)
(4階の展望室から房総半島や伊豆半島が一望できる小田原城)
その他、平山城には次のような城があります。
① 姫路城
赤松定範が築き、豊臣秀吉や池田輝政が大改修を行って、西日本最大規模の城になりました。
② 鶴ヶ城(会津若松城)
元中元年(北朝:至徳元年。1384年)に蘆名直盛が築いた東黒川館が始まり。
蒲生氏郷が文禄元年(1592年)に城下町の整備を始め、「鶴ヶ城」と改めました。
③ 小田原城
応永24年(1417年)に大森頼春が築いた小田原城。
田畑を含む城下を塀で囲んだため、籠城しながら食料を生産することができました。
上杉謙信による度重なる城攻めにも耐えた小田原城は難攻不落の城と呼ばれました。
平城のメリットとデメリット、特徴
平野部に築かれた平城。
山城や平山城に比べて、防御力が弱い印象をもつ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
メリット
平城のメリットをみていきましょう。
多くの兵を収容できる
城と町が隣接していたため、兵を城下に住まわせることができました。
敵が奇襲すれば、招集をかけるだけですぐ兵が集まりました。
また、城郭の要所に虎口を複数設け、兵が自由自在に出入りすることができるようにしました。
城下町が発展しやすい
城下町を塀や土塁で囲み、必要物資を町ですぐ調達できるようにしました。
そのため、商業が活性化し、城下町が発展しました。
デメリット
平城は近くの山から丸見え。
本丸の場所が見てわかるため、敵の遠隔攻撃が当たりやすく、防御力が劣りました。
特徴
水堀や石垣で守備を固めた平城。
民を多く住まわせられる、城下町が発展しやすい平城は政治・経済の拠点向きです。
-500x334.jpg) (躑躅ヶ崎館跡は、現在は武田神社になっている)
(躑躅ヶ崎館跡は、現在は武田神社になっている)
平地に土塁と堀で囲った
・鎌倉時代初期から南北朝時代にかけて作られた武士の住まい・方形館
・室町・戦国時代にかけてつくられた守護所・館
が平城のルーツ。
戦国時代以前は山城が中心で、平城はほとんど築かれませんでした。
戦国後期になると、城に対して、軍事拠点の他、政治・経済の拠点としての役割を求めるようになります。
そのため、交通や商業の要衝である平地に城を築きました。
 (約260年にわたって尾張徳川家の居城になった名古屋城)
(約260年にわたって尾張徳川家の居城になった名古屋城)
① 躑躅ヶ崎館
永正16年(1519年)に武田信虎が築いた躑躅ヶ崎館。
武田氏の本拠地で、居館と家臣団の屋敷や城下町が一体になっています。
② 名古屋城
慶長14年(1609年)に徳川家康が築いた名古屋城。
名古屋城は濃尾平野を一望して監視できる軍事的な要地にあたりました。
③ 二条城
慶長6年(1601年)に徳川家康が築いた二条城。
足利氏、織田氏、豊臣氏も京都市街地に城を築きましたが、徳川宗家の城だけが現存しています。
まとめ:城の特徴を知ると、その時の情勢がわかる!
山城、平山城、平城のメリットとデメリット、特徴を紹介しました。
守りやすく攻めにくい山城。
政治・経済の拠点向きの平城。
山城と平城のいいところどりをした平山城。
戦国武将・大名は情勢に合わせた城を築きました。
それぞれのメリットとデメリットを理解すれば、城巡りがもっと楽しくなるのではないでしょうか。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()