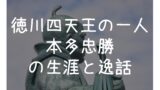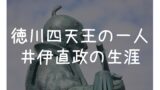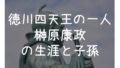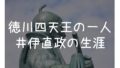徳川四天王の一人・榊原康政は、
① 徳川家康と徳川家康の三男・徳川秀忠にも忠義を尽くす
② 井伊直政の次男・井伊直孝に優しい言葉をかけられる
など、いわゆるデキる男でした。
榊原康政の3つの逸話を紹介します。
檄文で豊臣秀吉を怒らせた
天正12年(1584年)に、徳川家康・織田信雄と豊臣秀吉の間で勃発した小牧・長久手の戦い。
戦がまさに始ろうとしているその時、榊原康政は豊臣秀吉を痛烈に批判する檄文を飛ばしました。
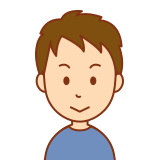
織田信長から大きな恩を受けておきながら…
豊臣秀吉は三男・織田信孝を殺し、次男・織田信雄をも討とうとしている!
織田信雄から協力を要請されて豊臣秀吉と戦うこととなった徳川家康。
織田信雄の協力要請を豊臣秀吉と戦う理由にするより、
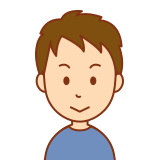
恩を仇で返そうとしている悪(豊臣秀吉)を退治する!
というほうが徳川軍の士気も高まります。

榊原康政の檄文を読んだ豊臣秀吉は図星だったのか激怒。
榊原康政の首を討ち取った者には特別に恩賞を渡すと約束しました。
織田信雄と豊臣秀吉が和睦し、小牧・長久手の戦いは終結。
徳川家康と豊臣秀吉が和睦することになると、榊原康政は徳川家康の使者として豊臣家に出入りしました。

戦の前には、榊原康政の首をなんとしても討つと息まいていた豊臣秀吉。
榊原康政は火の中に入っていくような想いだったかもしれません。
ところが、榊原康政と面会した豊臣秀吉は、
・徳川家康に対する忠義を褒め称える
・従五位下式部大輔の官職を贈る
などしました。
豊臣秀吉が榊原康政を家臣に引き入れようとしていたのかどうかは分かりません。
でも、豊臣秀吉からみても、榊原康政が素晴らしい武将だったということですね。
徳川秀忠をかばった
慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが勃発。
中山道を通った徳川家康の三男・徳川秀忠は、信州上田城で真田昌幸・信之親子と戦うこととなりました。
荒天で決着がなかなかつかないうえに、徳川秀忠は最終的に真田親子を討つことができませんでした。
徳川秀忠が関ヶ原に到着したのは、なんと、関ヶ原の戦いが終わった5日後でした。
☑ 上田合戦でもこれといった手柄をあげられなかった
ため、徳川秀忠は徳川家康から責められました。
でも、信州上田の天候が悪くなるなど、徳川秀忠には予測できなかったこと。
徳川秀忠は関ヶ原の戦いに間に合わなかった理由を徳川家康に説明しようと、面会を求めました。

ところが、徳川家康は「会うつもりはない」と言って断り続けました。
榊原康政は真田親子を相手にしないよう進言し続けていましたが、最終的に上田合戦に参戦した榊原康政。
この時、榊原康政は、
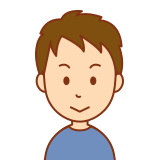
自分が武功をあげられなかったからです!
と言って、徳川秀忠をかばいました。
更に、「反省しようとしている息子に会わないのは、いかがなものでしょうか」と諫言。
確かに、主君の息子をかばうことは、家臣の役目かもしれません。
でも、榊原康政が責任を追及されて処罰される可能性があります。
にも関わらず、榊原康政は自己を顧みず、主君の息子をかばいました。
徳川家康から、そして、徳川秀忠からより厚く信頼を寄せられることとなりました。
この6年後の慶長11年(1606年)、榊原康政は毛嚢炎を患います。
榊原康政は江戸から80キロメートルも離れた館林城で暮らしていました。
でも、徳川秀忠は医者を手配したり、薬や見舞いの品を贈ったりしました。
徳川秀忠は榊原康政に感謝をしていたんですね。
徳川四天王と仲が良かった
同じく徳川四天王として名を連ねる酒井忠次、本多忠勝、井伊直政とは親友であり、良きライバルでした。
酒井忠次とは、姉川の戦いで武功を競いました。
二人の武功を見比べた徳川家康は、榊原康政のほうがより武功をあげていると評価しました。
同い年の本多忠勝は親友といっても過言ではないほど仲良し。
本多忠勝とは、武田勝頼が支配下に置いていた長篠城攻めで武功を競いました。
13歳年下の井伊直政とは一心同体の兄弟のような関係。
・「井伊直政より私が先にこの世を去ったら、井伊直政は病を患うだろう」
・「私より井伊直政が先にこの世を去ったら、間もなく私も去るだろう」
とよく口にしていました。

結果、井伊直政は慶長7年(1602年)に榊原康政を残してこの世を去ります。
榊原康政は井伊直政の次男・井伊直孝を気遣い、「何かあれば、遠慮せずに言うように」と言いました。
この時、井伊直孝は12歳。
異母兄・井伊直勝も同じく12歳だったため、榊原康政の申し出は心強かったのではないでしょうか 。
まとめ:榊原康政は主君、友達思いだった
榊原康政の3つの逸話を紹介しました。
一度は激怒した豊臣秀吉からも好かれた榊原康政。
誰の目から見ても、榊原康政はデキる男だったのではないでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()