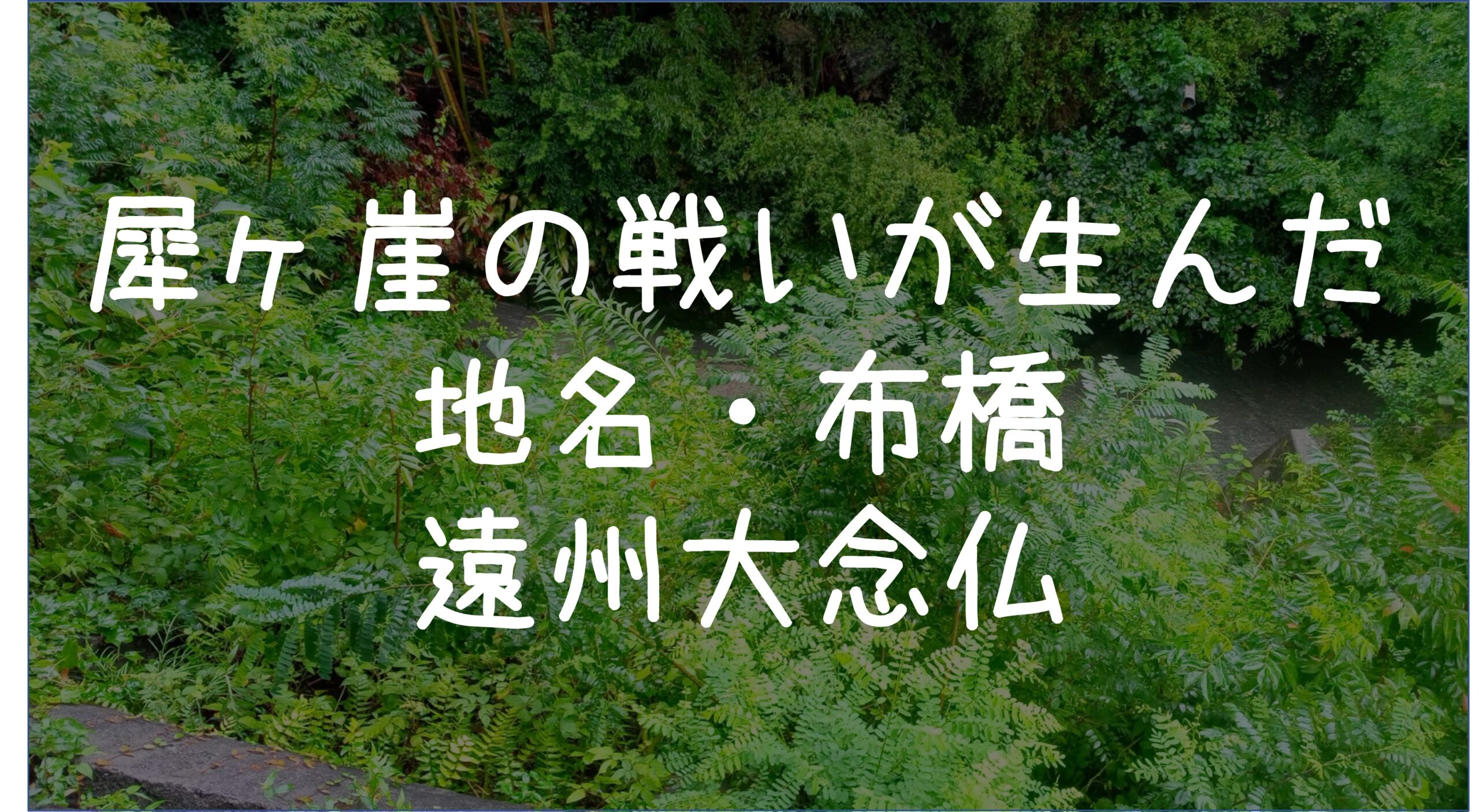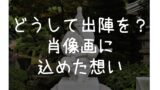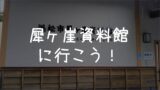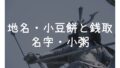三方ヶ原の戦いで武田信玄に破れ、浜松城に逃げ帰った徳川家康。
でも、その日の夜、徳川家康は犀ヶ崖で武田軍に再び挑みました。
徳川家康と武田信玄の犀ヶ崖の戦いが由来の地名・布橋、遠州大念仏を紹介します。
犀ヶ崖の戦いとは?
犀ヶ崖の戦いとは、元亀3年(1572年)12月22日の三方ヶ原の戦いのすぐ後に犀ヶ崖で起きた戦いを指します。
・二俣城の戦い
・三方ヶ原の戦い
で大敗した徳川家康が武田信玄に仕返しした夜襲です。
浜松城で籠城するつもりが、三方ヶ原台地に出陣し、不利な形で戦うこととなった徳川家康。
・戦う準備が整っていなかったこと
・武田信玄の率いる兵が徳川家康の率いる兵の2倍を超えていたこと
から、戦闘開始後わずか2時間で決着がつきました。
武田軍に首を狙われ、命からがら浜松城になんとか逃げ帰った徳川家康。
「このまま戦を終わらせてはいけない」と思い、家臣・大久保忠世、天野康景を呼び出します。

徳川家康は大久保忠世と天野康景に夜襲を命じました。
三方ヶ原の戦いに勝利した武田信玄は、浜松城の北にある犀ヶ崖に陣営を張り休んでいました。
そこで、徳川家康は浜松城のすぐ近くにあった普済寺に火をつけて、浜松城が炎上しているように見せかけました。

そして、「徳川軍が敗北したから浜松城が燃えているんだ」と武田軍が気を緩ませた隙に、陣営の背後から発砲。
織田信長が援軍に駆けつけたんだと勘違いした武田軍は大混乱。
武田軍は崖のある方向へ逃げ、100人を超える兵が崖に落ちていきました。
徳川家康の恐ろしさを知った武田軍は、浜松城を攻めず西へ向かいました。
徳川家康は三方ヶ原の戦いでは敗北しましたが、犀ヶ崖の戦いでは武田信玄の撃退に成功したんですね。
武田軍を夜襲したのは、大久保忠世と天野康景の独断かもしれません。
犀ヶ崖の戦いが由来の地名・布橋
甲斐国を拠点とする武田信玄は、遠江の地形に詳しくなかったかもしれません。
でも、陣営を張る以上、武田軍も周辺の下調べはしていたはずです。
実は、これも徳川家康の秘策。
武田軍は崖の向こう側に移動しようと、橋を渡ります。
でも、橋はただの布で、武田軍は次々と崖に落ちてしまいました。
このエピソードから、犀ヶ崖の付近に、布橋という地名が誕生しました。
犀ヶ崖の戦いが由来の遠州大念仏
犀ヶ崖の戦いで武田軍に一矢報いた徳川家康。
多くの家臣を失った徳川家康は多少スッキリしたかもしれません。
ところが、犀ヶ崖の谷底からうめき声が聞こえるようになります。
また、犀ヶ崖の戦いの近くで怪我をする人が続出。
やがて、
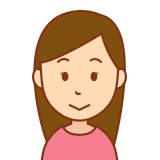
うめき声の主は、犀ヶ崖の戦いに落ちて亡くなった武田軍だ!たたりだ!
という噂が広がり、怖がられるようになりました。
そこで、徳川家康は三河から僧・了傅を招きました。
第13代住職・登誉天室は切腹を思いとどまらせ、了傅と共に徳川家康を支えました。
それ以来、了傅は徳川家康から厚く信頼されていました。
了傅は七日七晩太鼓と鉦(かね)を鳴らして供養。
うめき声は聞こえなくなり、また、怪我をする人もいなくなりました。

以降、徳川家康は三つ葉葵の紋付羽織を着て踊る念仏踊りを奨励します。
この念仏踊りは遠州大念仏に発展しました。
毎年7月15日には犀ヶ崖で、
・三方ヶ原の戦い
・犀ヶ崖の戦い
で亡くなった兵の霊を慰める遠州大念仏が行われています。
まとめ:徳川家康もたたりには勝てない!
徳川家康と武田信玄の犀ヶ崖の戦いが由来の地名・布橋、遠州大念仏を紹介しました。
犀ヶ崖の戦いで武田軍を撃退した徳川家康。
三方ヶ原の戦いで負けた悔しさを多少晴らすことができたかもしれません。
でも、代わりに、犀ヶ崖に落ちた武田軍の霊に悩まされることとなりました。
犀ヶ崖では、毎年7月15日に遠州大念仏が行われています。
犀ヶ崖の戦いが生んだ遠州大念仏、そして、浜松銘菓「布橋の雪」を楽しんでみてはいかがでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()