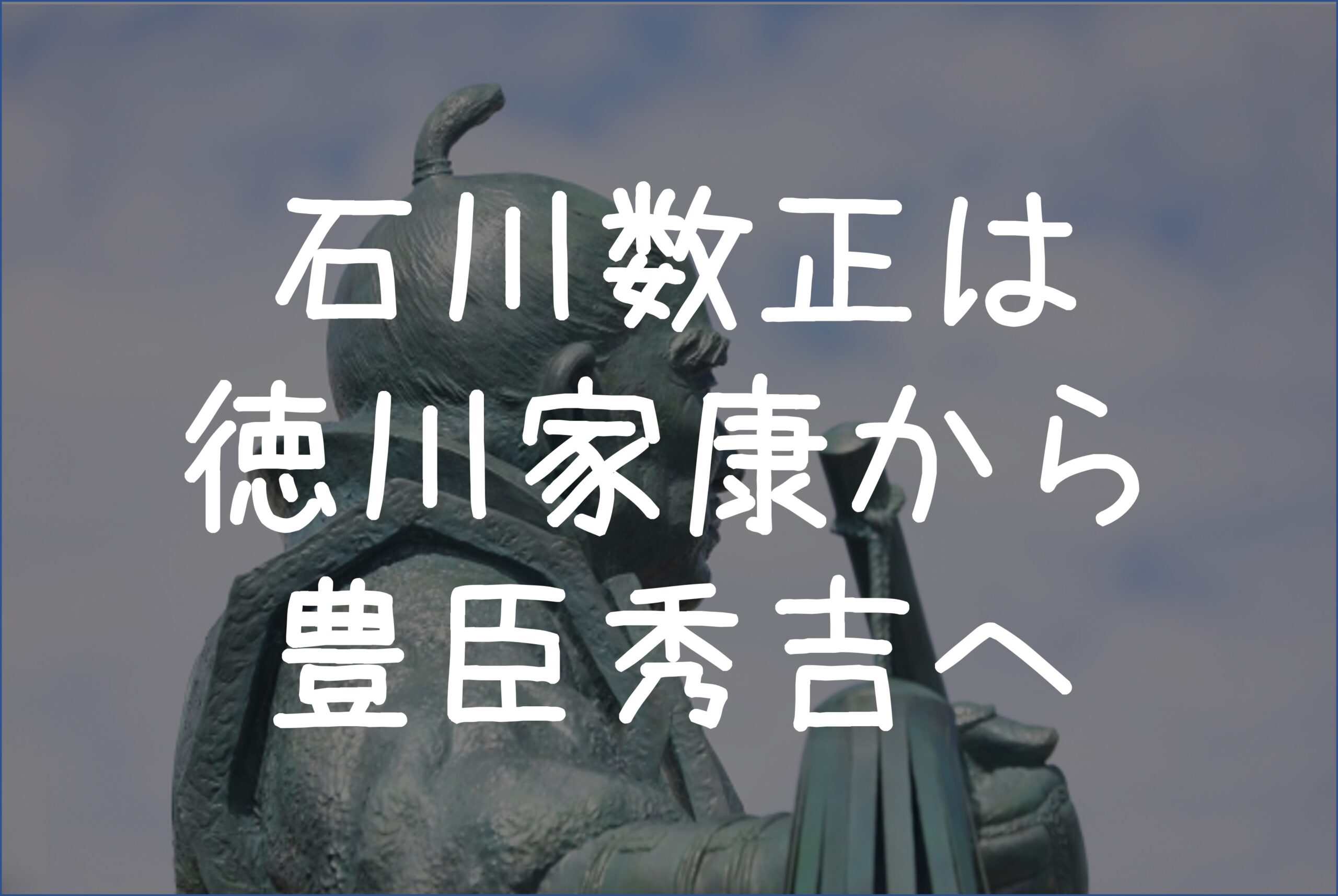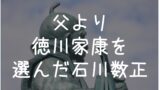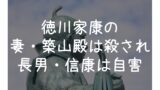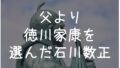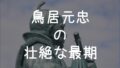徳川家康の片腕とも言われた家臣・石川数正。
ところが、ある日突然、徳川家康のもとを離れ、豊臣秀吉の家臣となりました。
何故、石川数正は出奔して、豊臣秀吉の家臣となることを選んだのでしょうか。
石川数正が徳川家康から豊臣秀吉に出奔した時期と理由、子孫のその後を紹介します。
石川数正が徳川家康から豊臣秀吉に出奔した時期
出奔(しゅっぽん)とは、逃亡することを指します。
石川数正が徳川家康を出奔したのは、天正13年(1585年)。
小牧・長久手の戦いで、徳川家康と豊臣秀吉が戦った翌年です。

三河の武士は主君に忠実に仕えることで有名。
実際、徳川家康を出奔したのは石川数正ぐらい。
・明智光秀を代表とした謀反が度々発生していた織田家臣
・穴山梅雪をはじめとした重臣が次々と裏切った武田家臣
に比べて、徳川家臣の忠誠心と団結力は強かったということができます。
そのため、井伊直政や本多忠勝など、徳川家康に強い忠誠心を抱いていた家臣は石川数正を批判しました。
石川数正がこのような忠誠心と団結力の強い徳川家臣を出奔したなんて、謎は深まるばかりです。
石川数正が徳川家康から豊臣秀吉に出奔した理由
紹介したように、石川数正が徳川家康を出奔したのは天正13年(1585年)です。
小牧・長久手の戦いで、石川数正は徳川家康と豊臣秀吉の和睦を成功させました。
そのため、石川数正は徳川家康のいない場で豊臣秀吉と接触する機会があったと考えられます。
また、出奔し、豊臣秀吉の家臣となった後すぐ、河内や信濃松本で所領を与えられています。
「家臣になったら、褒美を与える」など、石川数正は高待遇を約束されていたのかもしれません。

ただ、三河一向一揆では、石川数正は父と対立してまで徳川家康に仕えました。
褒美に釣られるような人物ではなかったと思います。
そこで、私は石川数正が出奔した理由を次のように考えています。
徳川家康が有利になるよう事を運びたかったため
小牧・長久手の戦いでは、(勝敗はつかなかったものの)徳川家康が優勢でした。
徳川家康に協力を要請した織田信雄が豊臣秀吉と無断で和睦したため、徳川家康は軍を退却せざるを得ませんでした。
面子を潰された徳川家康と豊臣秀吉の仲をとりもった石川数正。
豊臣秀吉から、
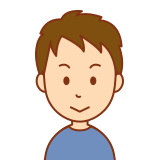
和睦を成功させたければ、私の家臣になるように!
と迫られた可能性も捨てきれません。
また、豊臣家の情報を徳川家に流そうと、豊臣秀吉のもとに身を寄せたとも考えられます。
もちろん、根拠はありません。
でも、一向宗から浄土宗に改宗してまで、三河一向一揆を鎮圧した石川数正であればとり得る行動です。
徳川家臣の中で孤立したから
小牧・長久手の戦いで豊臣秀吉と和睦を結んだことについて、批判する徳川家臣がいました。
徳川家康が優勢だったので、批判的な意見が出るのは当たり前。
でも、石川数正は批判され続けたり、家臣の中で孤立したりすることに耐えられなかったのかもしれません。
信康の切腹を許せなかったから
徳川家康の長男・信康は、
① 対立していた武田家と内通していた
② 妻・徳姫に横暴な振る舞いをしていた
として、義父・織田信長から切腹するよう命じられました。
徳川家康は信康をかばうことなく、天正7年(1579年)、信康を二俣城に幽閉したうえで切腹させました。
信康の後見人だった石川数正は、徳川家康・信康親子に献身的に仕えました。
三河一向一揆で父と対立してまで徳川家康に仕えた石川数正は、第二の父として信康に接していたかもしれません。
そのため、信康を助けようとしなかった実の父・徳川家康を許せなかったのではないでしょうか。
小笠原貞慶の内通に責任を感じたから
天正10年(1582年)の本能寺の変で主君・織田信長を失った小笠原貞慶。
小笠原貞慶は徳川家康の家臣となりました。
この時、徳川家康に忠誠を誓うべく、小笠原貞慶は長男・小笠原秀政を人質として差し出します。
徳川家康は小笠原秀政を石川数正に預けました。

ところが、小笠原貞慶は豊臣秀吉と内通していたことが発覚。
小笠原秀政を預かっていた石川数正は、
① 内通を見抜けなかったこと
② 小笠原秀政を止められなかったこと
に責任を感じ、徳川家康のもとを去る選択をしました。
石川数正の子孫のその後
天下分け目の戦いと呼ばれる関ヶ原の戦い、大坂の陣を経て、徳川家康は天下統一を果たします。
徳川家康を裏切った石川数正の子孫のその後はどうなったのでしょうか。
長男・康長
天文23年(1554年)生まれの石川康長は、石川数正と共に徳川家康に仕えていました。
徳川家康の次男・結城秀康が豊臣秀吉の養子になると、結城秀康と共に大坂に移りました。

石川数正が出奔すると、石川康長は大坂にそのまま居座り、豊臣秀吉に仕えました。
石川数正が亡くなり家督を継ぎ、慶長2年(1597年)には豊臣姓を贈られました。
でも、豊臣秀吉の死後、徳川家康に再び仕えます。
慶長5年(1600年)に勃発した関ヶ原の戦いでは東軍として参戦し、所領を安堵されました。
ところが、慶長18年(1613年)10月に起きた大久保長安の不正に伴って改易されます。
豊後国佐伯に流罪となり、寛永19年(1642年)12月に89歳で亡くなりました。
次男・康勝
兄・石川康長同様、大久保長安の不正に連坐して改易された後、交流のあった豊臣秀頼に仕えました。
慶長19年(1614年)の大坂の陣には、豊臣方として参戦し討死しました。
三男・康次
兄・康長、康勝同様、大久保長安の不正に連坐して改易されましたが、その後の消息は判っていません。
まとめ:石川数正の出奔理由には諸説有り!
石川数正が徳川家康から豊臣秀吉に出奔した時期と理由を紹介しました。
代々松平家(徳川家)に仕えてきた先祖を裏切り、豊臣秀吉に仕えた石川数正。
徳川家康が江戸幕府を開いた時、石川数正は既にこの世を去っていましたが、
① 徳川家康を裏切り、豊臣秀吉に仕えたことを後悔したのか
② 徳川家康が江戸幕府を開き、太平の世を築いたことを喜んだのか
あの世の石川数正はどのような心情だったのでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()