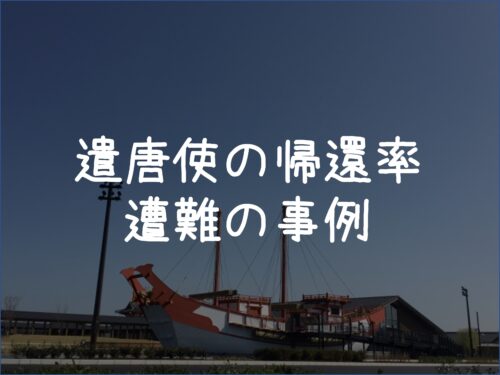
いつの時代も、航海には危険がつきもの。
はるか昔に、日本と唐を行き来していた遣唐使も度々窮地に立たされました。
遣唐使の帰還率(生存率)、遭難者の帰国方法、遭難した理由を紹介します。
遣唐使の帰還率(生存率)は?
現在の航海のように、到着地をピンポイントで絞り込むことができなかった遣唐使。
荒波を超えて唐に渡った、日本に戻った遣唐使の中には、もちろん、遭難を経験した人物がいます。
遣唐使は全部で20回行われたと考えられていますが、
・第6回遣唐使は日本を出発しなかった
・第11回遣唐使は何らかの事情で停止した
・第14回遣唐使は船が破損して停止した
・第15回遣唐使は風が吹かず停止した
・第20回遣唐使は菅原道真の上奏によって停止した
ため、実際に日本を出発したのは15回です。
また、時代によって異なりますが、
☑ 第7回遣唐使より前は2隻
☑ 第8回遣唐使より後は4隻
で向かうことがほとんどでした。
【第2回遣唐使】
往路にて、2隻中、第2船が薩摩沖にて遭難
【第4回遣唐使】
往路にて、2隻中、第1船が南海の島・爾加委に漂着
【第10回遣唐使】
復路にて、4隻中…
① 第1船が種子島に漂着
② 第2船が唐に漂着
③ 第3船が崑崙国に漂着
④ 第4船が難破
【第12回遣唐使】
復路にて、4隻中…
① 第1船が座礁し安南に漂着
② 第3船が紀伊国太地(現在の和歌山県東牟婁郡太地町)に漂着
③ 第4船は火災に遭うも薩摩国石籬浦(現在の鹿児島県揖宿郡頴娃町)に無事漂着
【第18回遣唐使】
往路にて、4隻中…
① 第3船が肥前松浦郡で座礁して遭難するも、大宰府に帰還
② 第4船も遭難したが無事に帰還
【第19回遣唐使】
① 往路にて、4隻中、1隻が遭難し、揚州の海岸に乗り上げて大破
② 復路にて、1隻が復路で南海の島に漂着するも、大隈国(現在の鹿児島県)に無事漂着
と伝えられています。
つまり、実際に日本を出発した15回の遣唐使のうち、6回が1隻以上遭難しました。
船の数を考えずに、回数だけで計算すると、遭難率は40%ということになります。
そのため、帰還率(生存率)は60%以上と考えるのが正しいかもしれません。
遭難者の帰国方法
紹介したように、遭難しても帰国した遣唐使が多くいます。
では、遭難した遣唐使はどのようにして帰国したのでしょうか。

第10回遣唐使を例にみていきましょう。
第10回遣唐使では、
① 大使・多治比広成
② 副使・中臣名代
③ 判官・平群広成(と秦朝元)
が海を渡りました。
734年10月、4隻の遣唐使船に、4人は責任者として一人ずつ乗り込み、唐を出発しました。

ところが、出発してすぐに、4隻全てが強風によって遭難してしまいます。
多治比広成
多治比広成が乗っていた船は、11月に種子島に漂着しました。
8世紀には、種子島は律令国家の支配下だったため、多治比広成は無事帰国することができました。
中臣名代
中臣名代が乗っていた船は、東南アジア海域まで流されます。
半年かけて、広州(広東省広州市)にたどり着きました。
中臣名代は唐の第9代皇帝・玄宗(李隆基)に謁見し、道教を学びたいと申し出ました。
玄宗は儒教や仏教より、道教を大切にしていました。
そこで、中臣名代は道教を学ぶ姿勢を見せて、玄宗に気に入ってもらおうと考えたんです。
道教を学び始めて8ヶ月が経った735年11月。
中臣名代は道教を日本に広めたいと申し出て、帰国することが許されました。
遣唐使船を修理し、736年8月に無事帰京を果たしました。
道教を学びたい、日本に広めたいと言ったのは、帰国するためだったことがよくわかりますね。
平群広成
平群広成が乗っていた船は崑崙国(現在のベトナム)に漂着しました。
言葉が通じなかったため、現地人に捕らえられ、90人を超える遣唐使が亡くなりました。
平群広成を含む生き残った4人は崑崙国から逃げ出しました。

玄宗は唐の六都護府の一つである安南(ハノイ)都護府に命じて、4人が唐に入国できるよう手配。
こうして唐に入国した平群広成は、当時唐に留学していた阿倍仲麻呂を頼ります。
平群広成は「渤海国(中国東北部及び朝鮮半島北部)を経由して帰国したい」と言いました。
玄宗はその申し出を聞き入れ、船や航海中に必要な衣食を用意しました。
738年10月、平群広成は渤海国に到着。
この頃、渤海国は日本に使節をちょうど派遣するところでした。
平群広成は渤海大使・胥要徳と一緒に、2隻の船で日本海を渡ることになりました。

ところが、胥要徳が乗っていた船は荒波に飲まれて転覆。
胥要徳は亡くなってしまいました。
平群広成は生き残った渤海使節を自分の船に乗せて、出羽(秋田県、山形県)にたどり着きます。
そして、739年10月にやっと帰京することができました。
遭難した理由
遭難する遣唐使を想像した時、
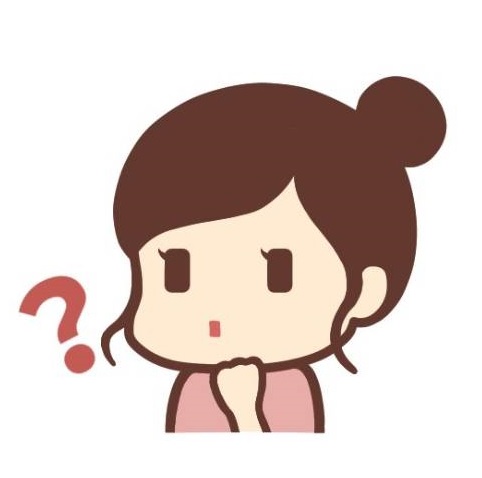
当時の船舶技術が低かったから、遭難したんじゃない?
と考える方も多くいらっしゃるかもしれません。
でも、遣唐使の遭難には、船舶技術のレベルよりも、日本や唐を出発した時期が大きく影響しています。
当時、日本は朝貢国であり、唐に派遣される遣唐使は朝賀に参列しなければいけませんでした。
そのため、遣唐使は朝賀に間に合うよう、大宰府を出発しました。
遅くとも9月までには、大宰府を出発しなければ、朝賀に間に合わなかったと考えられています。
また、遣唐使は留学を終えたらすぐに帰国しなければならず、9月に唐を出発した遣唐使もいます。
航海に適していない時期に出発したから、往路・復路で、転覆、漂流する遣唐使船があったんですね。
まとめ:遣唐使の出航は時期が適していなかった
遣唐使の帰還率(生存率)、遭難者の帰国方法、遭難した理由を紹介しました。
遣唐使の遭難率は40%ですが、帰国できた遣唐使が多く、帰還率(生存率)はもっと高いと考えられます。
朝賀に参列するために、台風の多い9月に出航した遣唐使。
出航する時期をずらしていれば、遣唐使はもっと安全に航海できたかもしれませんね。
遣唐使について知りたい方は、東野治之著「遣唐使」がおすすめ。
遣唐使が日本に持ち帰った物から与えた影響まで、知りりたいことがコンパクトにまとめられています。
ぜひ一度、「遣唐使」を読んでみてください。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()



