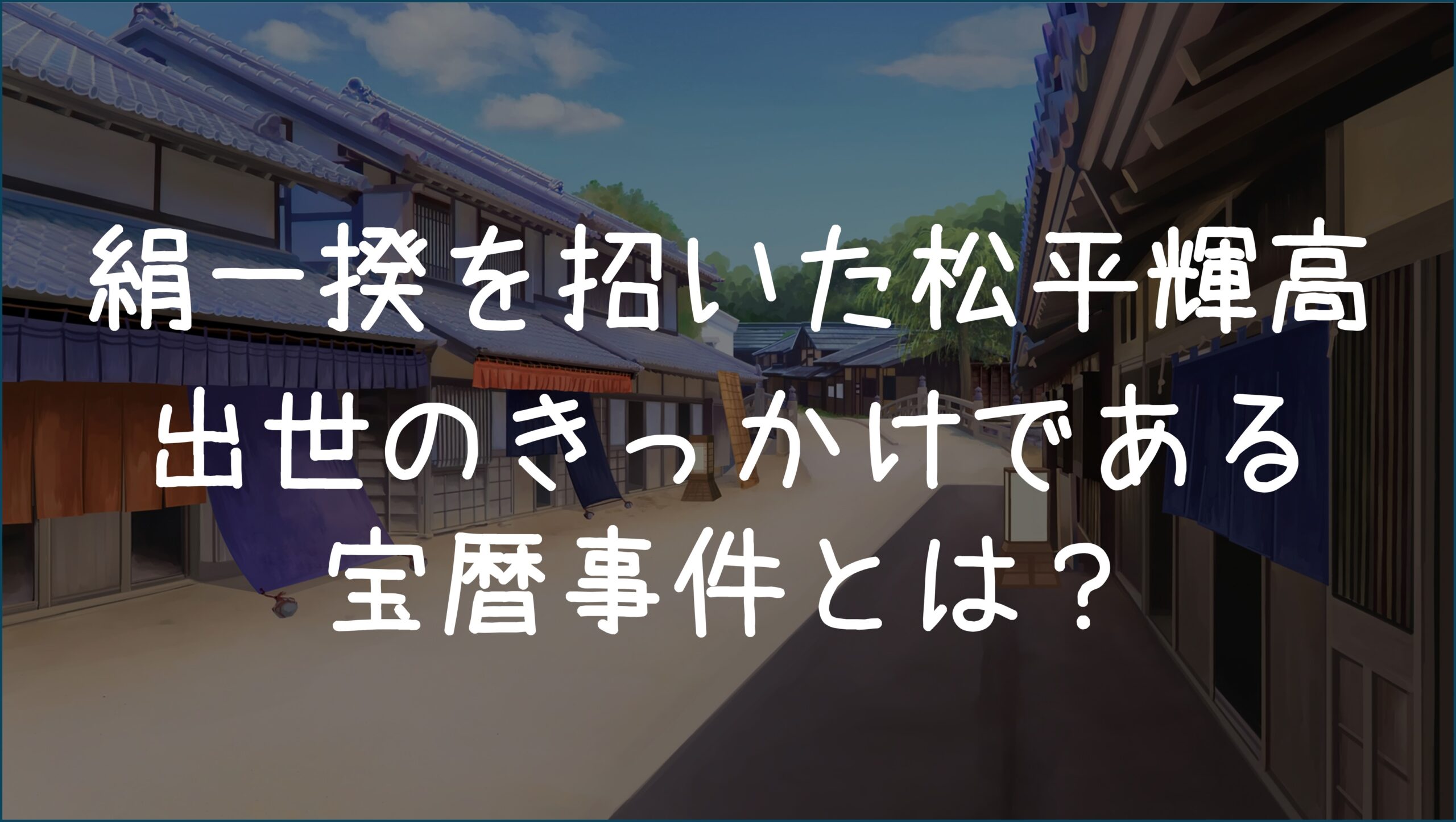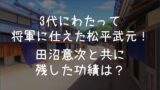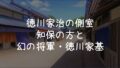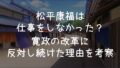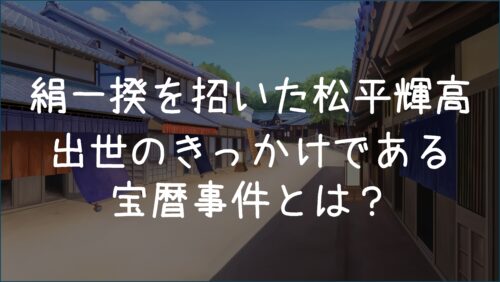
松平武元の死後、老中首座となった松平輝高。
その後、松平輝高は絹一揆を招いてしまいますが、そもそも何故老中首座にまで出世できたのでしょうか。
松平輝高の生涯と出世するきっかけになった宝暦事件を紹介します。
絹一揆を招いた松平輝高ってどんな人?
松平輝高は享保10年(1725年)生まれ。
高崎藩初代藩主・松平輝規のもとに長男として誕生しました。
老中首座になる
安永8年(1779年)、松平武元が亡くなると、後を継いで老中首座になります。
当時、老中首座は勝手掛も兼ねていました。
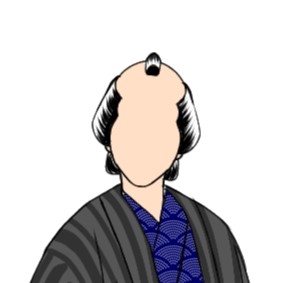
勝手掛とは、財政を管理する老中を指します。
具体的には、月番を務める他、
・勘定所役人から上申を受けた物の金額を決める
・金額が適正かどうかを見直す
などの仕事を行いました。
絹糸や綿の売買の改所を設置する
老中首座になった松平輝高は武蔵国と上野国の絹糸や綿の売買の改所の設置を決定。
47もの市場に10ヶ所の改所を置き、その品質の改め料として、
・反物1疋につき銀2分5厘
・糸100目につき銀1分
・真綿1貫目につき銀5分
を買主(問屋)に負担させることにします。
松平輝高のやり方に不満を抱いた老中もいましたが、松平輝高は勝手掛老中。
物の金額を決める立場にあります。
他の老中は口を挟むことができませんでした。
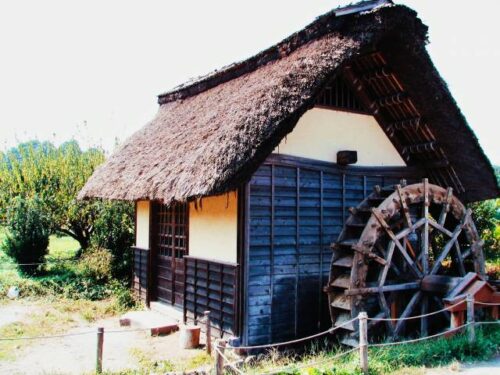
絹をつくり、販売していたのは農民。
当時、農民は原則として商売を禁止されていました。
ただ、農間と呼ばれる耕作の合間に稼ぐことは認められていました。
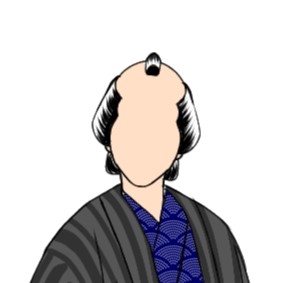
実は、副業である農間稼ぎこそ、農民にとって主業。
農民の厳しい生活を支える大事な仕事でした。
絹一揆が起きる
京都や江戸の都市問屋は上州の絹市に出向いて絹を買い求めます。
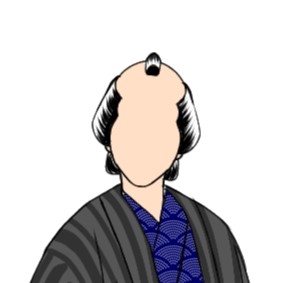
ところが、品質改め料を計算すると、とても購入する気になれません。
高い品質改め料をわざわざ支払って買わなくても、去年の在庫があります。
都市問屋は仕入れ(購入)を止め、絹市は成り立ちませんでした。
上州53ヶ村の農民は作った絹を全く売ることができませんでした。
「このままでは餓死してしまう」と危機感を抱いた農民は徒党を組みます。

・改所の設置に賛同した地主や商人の屋敷、家財を打ち壊す
・七日市藩陣屋を攻撃する
などしながら、高崎城下に押し寄せました。
そして、城を包囲して、改所の撤廃を求めます。
身の危険を感じた松平輝高は老中に相談することなく、一人で改所の廃止を決めます。
ところが、改所廃止のニュースは一揆勢になかなか届きません。
城を包囲した一揆勢と高崎藩の兵は衝突。
絹市が成り立たなかったことによる経済的損失はもちろん、人的被害をも出してしまいました。
老中在任のまま57歳で亡くなる
責任を感じた松平輝高は辞職願を出し、老中の座を退こうとしました。
でも、江戸幕府第10代将軍・徳川家治は受け入れませんでした。
天明元年(1781年)、老中在任のまま、松平輝高は57歳で亡くなりました。
出世のきっかけ・宝暦事件とは?
松平輝高が出世を遂げたのは、宝暦事件で手柄を立てたからです。

宝暦事件とは宝暦8年(1758年)に起きた弾圧事件です。
竹内式部は京都で公家に尊王論を説いていました。
尊王とは天皇を王者として尊崇すること。
言うまでもなく、江戸時代は幕府が天皇より強い権力をもっていました。
「幕府(将軍)より天皇を敬うべき」と説かれては、賛同した民が反乱を起こすかもしれません。
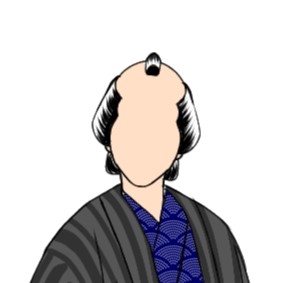
尊王思想は幕府にとって都合が悪く、竹内式部を追放刑に処して弾圧したんです。
この時、京都所司代を務めていたのが松平輝高。
松平輝高は竹内式部を追放し、幕府を救った一人だったんですね。
まとめ:京都所司代でなければ出世はなかったかもしれない…
松平輝高の生涯と出世するきっかけになった宝暦事件を紹介しました。
老中首座になった松平輝高は絹糸や綿の売買の改所を設置。
その結果、絹市は成り立たず、絹一揆を招いてしまいました。
松平輝高が出世を遂げたのは宝暦事件で手柄を立てたから。
宝暦事件が起きた時、松平輝高が京都所司代を務めていなければ、老中首座にまで登りつめることはなかったかもしれませんね。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」を楽しむなら、こちらのガイドブックがオススメです。

キャスト紹介と役にかける想い、登場人物の簡単な説明が載っています。
ガイドブックを読めば、ドラマに集中できること間違いなし!
手に取っていただきたい一冊です。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()