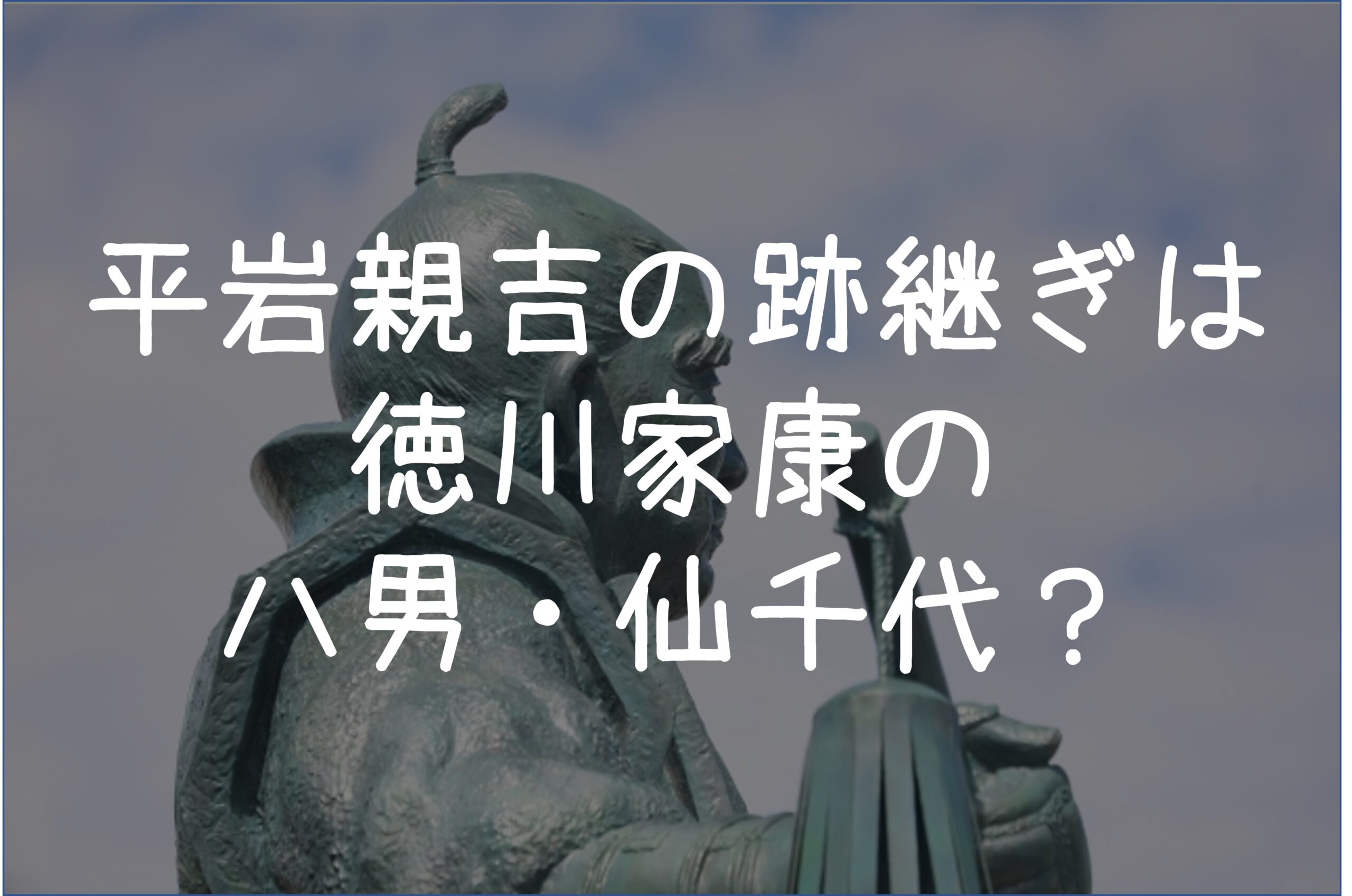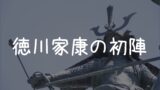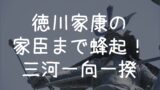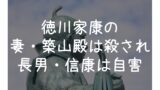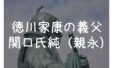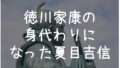70年間の人生のうちの65年間を、
① 徳川家康
② 徳川家康の長男・信康
② 徳川家康の九男・徳川義直
に捧げた平岩親吉。
徳川家康から信頼を寄せられた平岩親吉は、徳川家康の八男を養子に迎えました。
徳川十六神将・平岩親吉の生涯と徳川家康の子孫・仙千代を養子に迎えていたエピソードを紹介します。
徳川十六神将・平岩親吉の生涯
平岩親吉は徳川家康と同じ天文11年(1542年)の生まれ。
父・平岩親重と母・天野貞親の娘の間に次男として誕生しました。
・天文16年(1547年)、徳川家康が織田家の人質となると、平岩親吉は徳川家康に付き添って万松寺へ
・天文18年(1549年)、徳川家康が今川家の人質となると、平岩親吉は徳川家康に付き添って駿府へ
向かい、小姓(こしょう)として徳川家康を支えました。

小姓とは、いわゆる雑用係です。
そのため、主に年齢の若い者が就きましたが、若ければそれでいいというわけではありません。
・武芸に秀でていること
・作法を身につけていること
・幅広い知識をもっていること
が求められました。
徳川家康と一緒に初陣を迎える
永禄元年(1558年)に勃発した、徳川家康の初陣・寺部城の戦い。
実は、寺部城の戦いは平岩親吉の初陣でもありました。
三河一向一揆を鎮圧する
同い年で、幼い頃からずっとそばにいた平岩親吉は、徳川家康にとって親友のような、兄弟のような存在。
永禄6年(1563年)の三河一向一揆では、自身は一向宗(浄土真宗本願寺派)であるにも関わらず、徳川家康に従って一揆の鎮圧に貢献しました。
徳川信康の傅人となる
徳川家康から厚く信頼された平岩親吉は、徳川家康の長男・信康の傅人(養育係)に任命されます。
ところが、天正7年(1579年)、織田信長の娘・徳姫と結婚した信康が切腹に追い込まれてしまいました。
傅人として、徳川信康を近くで支えてきた平岩親吉は、
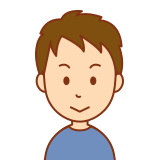
(信康が)切腹するような事態を招いたのは、自分の目が行き届いていなかったからだ
と言って、信康の代わりに切腹すると申し出ました。
でも、信康の切腹は免れず、責任を感じた平岩親吉は蟄居しました。
甲府城主となる
天正10年(1582年)、天正壬午の乱を経て、甲斐国を手に入れた徳川家康は平岩親吉を呼び戻します。
そして、徳川家康の命令に従って、平岩親吉は甲府城を築城しました。
慶長6年(1601年)には、甲斐国に戻り、自ら築城した甲府城主となり、6万3千石を領しました。
徳川義直の後見役となる
慶長8年(1603年)、徳川家康の九男・義直が甲斐25万石に封ぜられました。
幼い徳川義直は徳川家康のいる駿府で暮らし、平岩親吉は徳川義直の後見役に任命されます。
徳川義直に代わって、平岩親吉は甲斐国を統治しました。
慶長12年(1607年)、徳川義直が尾張藩主となると、平岩親吉も尾張に移り、政務を行いました。
また、犬山藩主として12万3千石に封ぜられました。
慶長16年(1611年)、名古屋城にて、平岩親吉は70歳で亡くなりました。
徳川家康の子孫・仙千代を養子に迎えていた
平岩親吉は徳川家康の父・松平広忠に仕えていた石川政信の娘と結婚していましたが、跡継ぎがいませんでした。
そこで、徳川家康は八男・仙千代を平岩親吉の養子として差し出しました。
ところが、仙千代は慶長5年(1600年)にわずか6歳で亡くなってしまいます。

跡継ぎを失った平岩親吉は、自身の犬山藩の所領を徳川義直に譲るように言い残して亡くなりました。
徳川家康は平岩氏を断絶させたくない一心で、平岩親吉の息子だという噂の子ども・堀隼人正重を探します。
そして、犬山藩の所領を継がせようとしました。
でも、堀隼人正重の母親が平岩親吉の息子だとは認めず、平岩氏は平岩親吉の死をもって断絶しました。
まとめ:徳川家康の願いは叶わず、平岩氏は平岩親吉の代で断絶!
徳川十六神将・平岩親吉の生涯と徳川家康の子孫・仙千代を養子に迎えていたエピソードを紹介しました。
戦国武将が自分自身の子どもを家臣の養子にするなんて、異例の出来事。
徳川家康が平岩親吉にどれだけ感謝していたかが分かりますね。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()