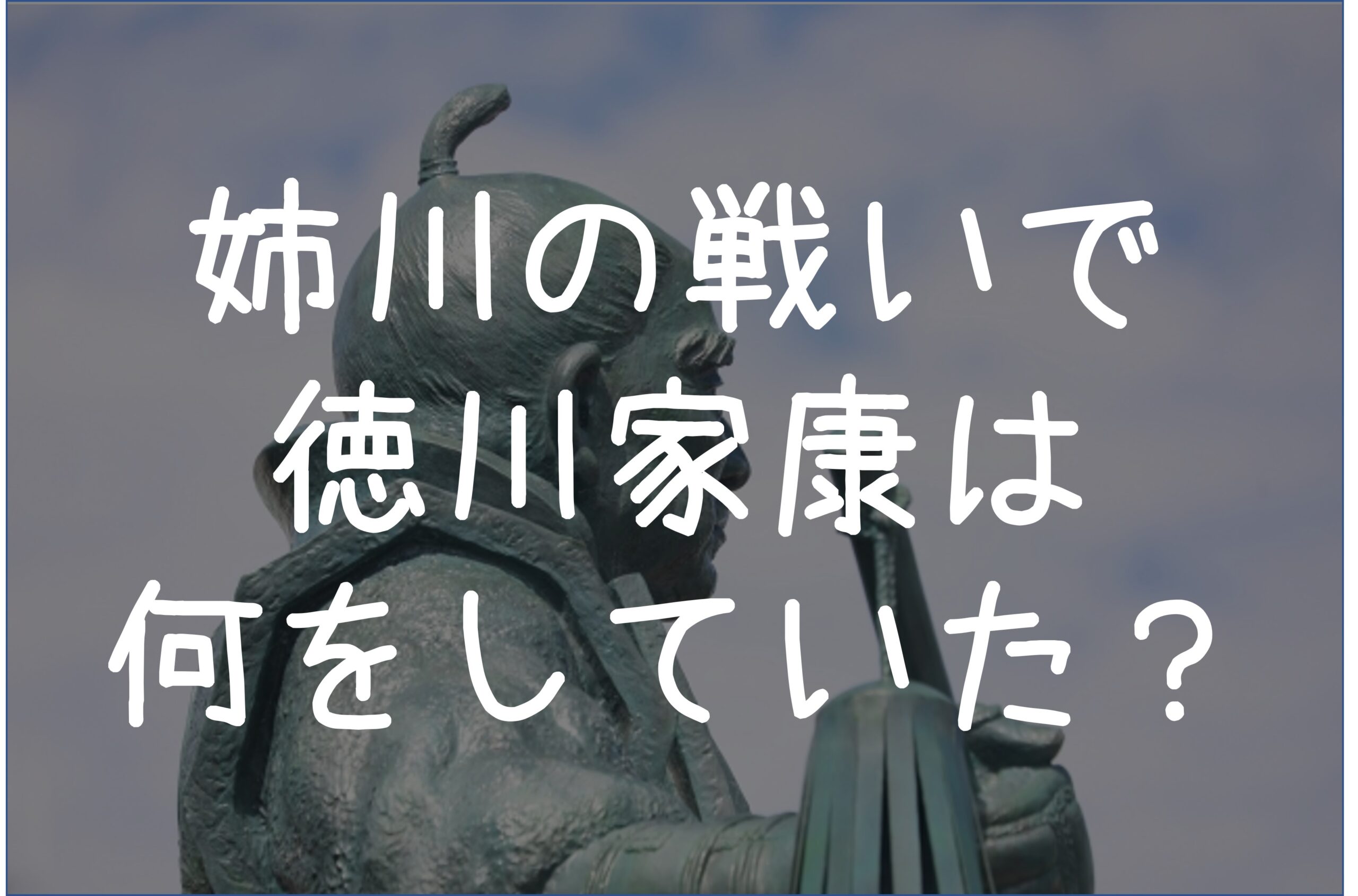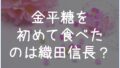元亀元年(1570年)4月に勃発した金ヶ崎の戦い(金ヶ崎の退き口)から2ヶ月後。
徳川家康は織田信長から援軍を再び要請され、自ら出陣しました。
織田信長が勝利した姉川の戦いにおける徳川家康の動きをわかりやすく解説します。
姉川の戦いとは?
姉川の戦いは元亀元年(1570年)6月に、
① 織田信長・徳川家康連合軍
② 朝倉義景の従甥である朝倉景健・浅井長政連合軍
の間で勃発した戦いです。
どちらの連合軍も兵力は1万3千人でしたが、敗北した朝倉・浅井連合軍は1100人もの損害を出しました。
6月15日、織田家臣・豊臣秀吉、竹中半兵衛の調略により、浅井家臣・堀秀村が織田信長に寝返りました。
・長比城(たけくらべじょう)
・苅安城
の守備を任されていました。
堀秀村は織田信長に城を明け渡し、織田信長は長比城に宿営しました。

小谷城を本拠地とする浅井長政を討つべく、6月21日、織田信長は小谷城下を焼き払います。
続いて、小谷城に向かおうとしましたが、まさに難攻不落と言っても過言ではない守りの堅さでした。
織田信長は2日間にわたって小谷城を攻めましたが、城内まで攻撃が届きません。
攻めあぐねているうちに、朝倉景恒率いる朝倉軍が木之本までやってきているという報告がありました。
そこで、織田家臣・柴田勝家は「横山城を攻略して、浅井長政をおびき寄せてはどうでしょうか」と提案。
6月24日、織田信長は退却し、横山城を陥落させ、麓にある龍ヶ鼻に本陣を構えました。
こうして、姉川を挟んで、
① 北に朝倉景健・浅井長政連合軍
② 南に織田信長・徳川家康連合軍
が陣を敷きました。

戦が始まって5時間半が経過。
優勢だった朝倉景健・浅井長政連合軍は織田信長・徳川家康連合軍の本陣に迫ります。
ところが、徳川家康のおかげで窮地を脱し、織田信長は勝利をおさめて、美濃に帰還しました。
姉川の戦いにおける徳川家康の動き
紹介したように、姉川の戦いで織田信長が勝利をおさめることができたのは、徳川家康のおかげ。
金ヶ崎の戦いを終えて、岡崎城に帰った徳川家康のもとに、織田信長から使者がやってきました。
出陣要請を聞いた徳川家康は早速準備に取りかかり、織田信長の本陣・龍ヶ鼻に到着しました。

そして、敵の戦略、動きに合わせて臨機応変に行動する遊撃隊をかって出ました。
徳川家康は岡山に本陣を構えて、敵を観察。
すると、朝倉軍の陣形が縦に伸びていることに気付きます。
姉川を渡って朝倉軍を側面から不意打ちするよう、徳川家康は榊原康政に命じました。

それまで、朝倉・浅井連合軍が優勢でしたが、榊原康政率いる徳川軍の攻撃により形勢は逆転。
敗走する朝倉軍を見た浅井軍は動揺し、不利な状況に陥ったため退却しました。
まとめ:徳川家康の戦の才能が開花し始めていた!
織田信長が勝利した姉川の戦いにおける徳川家康の動きをわかりやすく解説しました。
金ヶ崎の戦いに引き続き、ピンチに陥った織田信長を救った徳川家康。
織田家臣である豊臣秀吉も頭角を現していました。
この頃から、徳川家康と豊臣秀吉の戦いは始まっていたのかもしれませんね。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()