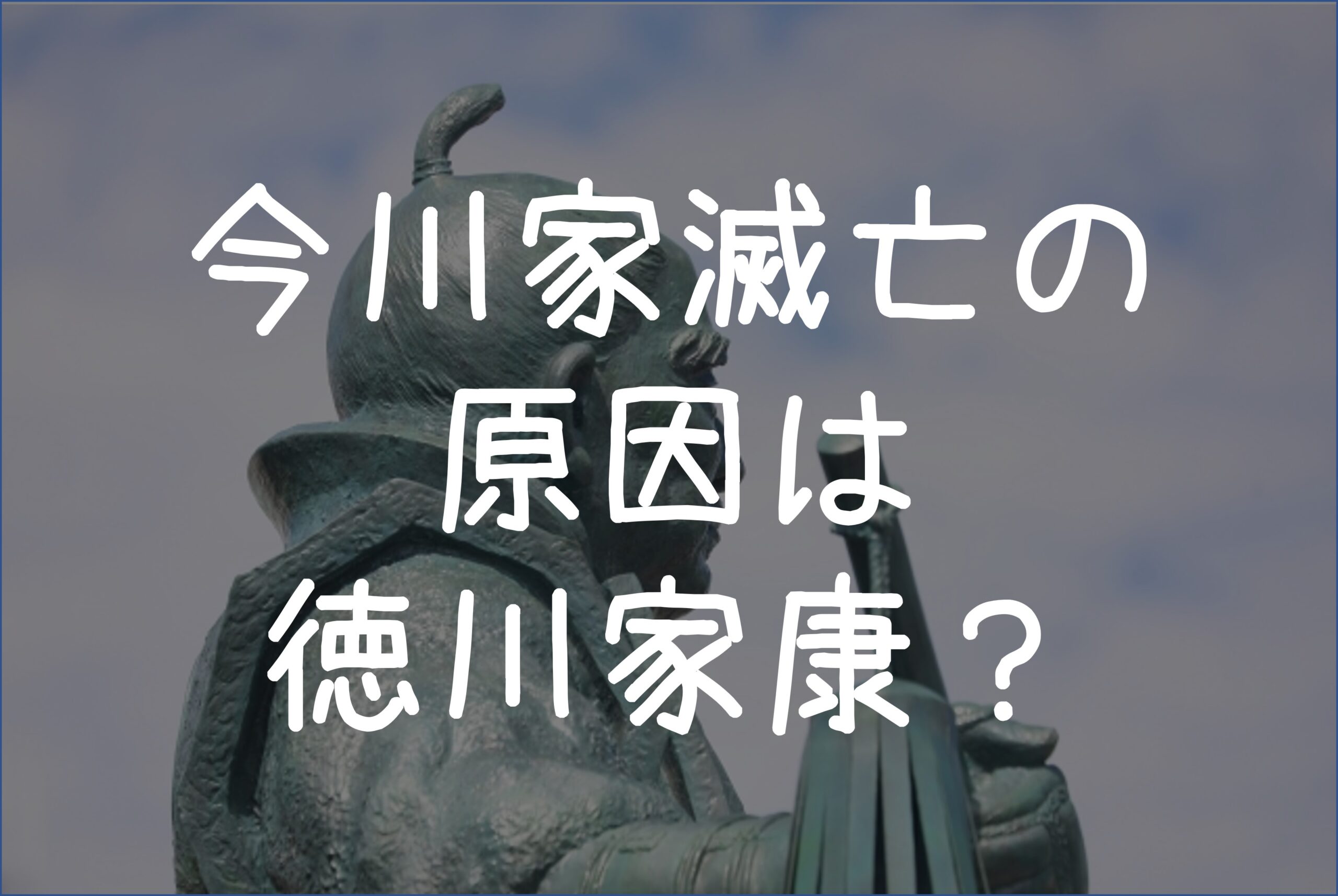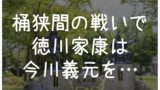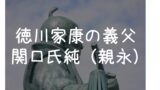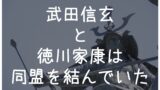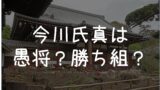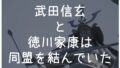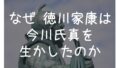「海道一の弓取り」と呼ばれる今川義元の跡を継いだ今川氏真。
戦国大名としての今川家は今川氏真の代で滅亡してしまいますが、今川家滅亡には徳川家康が大きく関わっています。
今川家滅亡の原因が徳川家康にあったとされる4つの理由を紹介します。
徳川家康が今川家を離反した
永禄3年(1560年)に勃発した桶狭間の戦いで、今川義元が織田信長に討たれました。
徳川家康は「跡を継いだ今川義元の長男・今川氏真が敵を討つ」と思っていました。
でも、今川氏真に織田信長と戦う気はありませんでした。
この時、徳川家臣は今川家から独立するよう進言。
鳥居元忠は今川義元に黙ってへそくりを貯め、徳川家康の独立に備えていました。
徳川家康は家臣の期待に応えようと、今川家を離反することを決意しました。

今川家を離反した徳川家康は今川家臣・鵜殿長照を討ちました。
また、今川家の人質となっていた正室・築山殿、長男・信康、長女・亀姫を取り戻した徳川家康。
この時、家族と引き換えに、今川家臣である築山殿の父・関口氏純を切腹させてしまいました。
徳川家康の独立によって、今川氏真は大事な家臣を次々と失いました。
徳川家康が武田信玄と手を結んだ
天文23年(1554年)、
① 駿河国・遠江国の今川義元
② 甲斐国の武田信玄
③ 相模国の北条氏康
は三者間で甲相駿三国同盟を結びました。
この時、今川義元は娘・嶺松院を武田信玄の長男・武田義信に嫁がせ、姻戚関係を築きました。

ところが、永禄10年(1567年)11月、嶺松院は離縁させられ、今川家に送り返されてしまいました。
この頃、武田信玄は「今川家を滅ぼして、遠江を分割しよう」と徳川家康に提案。
徳川家康は武田信玄の提案を受け入れ、手を結びました。
そして、武田信玄は駿河に攻め入り、徳川家康は遠江に攻め入りました。
徳川家康が掛川城を攻めた
武田信玄に駿府を占領された今川氏真は朝比奈泰朝が城主を務める掛川城に逃げました。

朝比奈家は東遠江の旗頭を代々務めていました。
今川家臣が次々と離反する中、今川氏真が最も信頼できる家臣は朝比奈泰朝でした。
今川氏真を掛川城に受け入れた朝比奈泰朝は城兵3000人を率いて、遠江に侵攻した徳川家康を相手に奮戦。
戦況は徐々に厳しくなりましたが、今川家は兵力が既になく、援軍は見込めません。

永禄12年(1569年)5月17日、朝比奈泰朝は、
① 城兵の命を奪わない
② 城兵の身の振り方を自由に選択させる
③ 今川氏真を殺さない
という3つの条件を提示して開城しました。
掛川城を出た今川氏真は掛塚湊(静岡県磐田市)に向かいます。
その後、船で蒲原(かんばら。静岡市清水区)に渡って、戸倉城に退去しました。
これにより、戦国大名としての今川家は滅亡しました。
徳川家康が約束を破った
紹介したように、掛川城主・朝比奈泰朝は3つの条件を出して開城しました。
一方、徳川家康は自ら次のような約束事を提示しました。
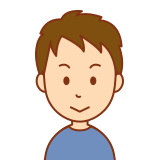
武田信玄を駿河から退去させたら、今川氏真を駿河国主に再びたてる!
ところが、徳川家康はこの約束を守りませんでした。
武田信玄の侵攻を受けた駿河は武田氏の支配下に置かれます。
武田信玄の死後、跡を継いだ武田勝頼が統治しました。
天正10年(1582年)、徳川家康は織田信長と共に武田勝頼を討ち、武田氏を滅ぼします。
でも、徳川家康は駿河を自らの支配下に置き、今川氏真に任せることなく統治し続けました。
まとめ:今川家滅亡の原因は徳川家康の裏切り
今川家滅亡の原因が徳川家康にあったとされる4つの理由を紹介しました。
徳川家康は武田勝頼から駿河を奪いましたが、駿河を今川氏真に返しませんでした。
徳川家康が今川氏真を駿河国主にたてていたら、戦国大名としての今川家は再興していたかもしれませんね。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()