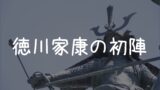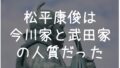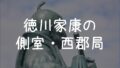端午の節句に飾る五月人形は、病気や事故などの災いから男の子を守ってくれるといわれています。
五月人形には、徳川家康をモチーフにしたものがありますが、どのような特徴があるのでしょうか。
徳川家康の五月人形の兜の特徴と意味、由来を紹介します。
徳川家康の五月人形の兜の特徴と意味
徳川家康の五月人形の兜の特徴と意味をみていきましょう。
特徴
徳川家康の五月人形の兜の特徴は2つあります。
大黒頭巾形
徳川家康の五月人形の兜は独特な形をしていますが、これは大黒天が被っていた頭巾がベース。

大黒天が被っていた頭巾の形をしているから、大黒頭巾形と呼ばれているんですね。
現在では、大黒天は七福神の一人として知られていますが、実はインド神話から誕生しました。
インド神話で描かれる大黒天は暗黒神。
漢字から想像できるように、暗黒で死を司る神だったんです。
ところが、中国、そして、日本へと伝来する過程で、いつの間にか福の神となりました。
発音が似ていることから勘違いし、福の神として崇拝するようになったのではないかといわれています。
※大黒天は仏教の神様で、大国主命は神道の神様なので、全く別の神様です。
大黒天のご利益は財福、出世開運、五穀豊穣などの金運から縁結びまで、多岐にわたります。
でも、紹介したように、大黒天は元々暗黒神で、死を司る神。
大黒天を信仰することで、現世における罪が軽くなり、極楽浄土に行けるとされていました。

また、大黒天には、戦を司る神という別の一面があります。
大黒天を信仰することで、戦に勝てるとされていました。
そのため、戦国時代には大黒天を守護神とする戦国武将が多くいました。
大黒頭巾形の兜は戦国時代を生き抜いた徳川家康の象徴となる兜なんですね。
歯朶の葉
大黒頭巾形の兜に飾られている歯朶(シダ)の葉も大きな特徴。
歯朶は枯れることがなく、また、葉の裏には胞子がたくさんあります。
そのため、歯朶は長寿、子孫繁栄を表しているとされてきました。
武士の平均寿命は42歳だったといわれる戦国時代に、徳川家康は75歳まで生きました。
また、16人もの子どもを授かりました。
歯朶の葉は長生きした、また、子だくさんだった徳川家康の象徴となる飾りなんですね。
意味
紹介した兜の特徴から、徳川家康の五月人形の意味は、
① 壁にぶつかってもめげない
② たくましい
③ 長生き
④ 子孫繁栄
となります。
男の子であっても、女の子であっても、いつかは親元を離れます。
子どもが壁にぶつかった時に、手を差し伸べてあげたくなります。
でも、壁にぶつかる度に手を差し伸べてあげることはできません。

・自分で考え、乗り越えていける子どもに育ってほしい
・長生きして、子どもや孫、ひ孫に囲まれるおじいちゃんになってほしい
という想いを抱いている親御さんにピッタリの五月人形といえるのではないでしょうか。
徳川家康の五月人形の兜の由来
徳川家康の五月人形の兜の特徴(大黒頭巾形、歯朶の葉)を紹介しました。
それは、徳川家康が実際に身に着けていた甲冑に由来しています。
永禄元年(1558年)に17歳で初陣を迎えた徳川家康。
75歳で亡くなるまでの58年間で、徳川家康はたくさんの防具を装備しました。
ただ、徳川家康の権力を確固たるものにした
・慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い
・慶長19年(1614年)の大坂冬の陣
・慶長20年(1615年)の大坂夏の陣
の3つの戦いで、徳川家康は歯朶具足という甲冑を身に着けていました。

実は、歯朶具足は徳川家康がデザインしたもの。
関ヶ原の戦いで出陣する前に、徳川家康は不思議な夢を見ました。
夢の中で、大黒天が武装していたんです。
徳川家康は甲冑師に指示を出し、夢の中で大黒天が装着していた甲冑をつくらせました。
関ヶ原の戦い、大坂の陣では、この歯朶具足を身に着け、必勝を祈願しました。
徳川家康が身に着けていた歯朶具足の兜の大きな特徴は、大黒頭巾形と歯朶の飾り。
そう、徳川家康の五月人形の兜は徳川家康が愛用していた歯朶具足を再現したものなんですね。
まとめ:徳川家康にあやかって子孫繁栄を願おう!
徳川家康の五月人形の兜の特徴と意味、由来を紹介しました。
徳川家康が愛用していた兜を飾って、
・戦国時代を生き抜いた
・長生きした
・子だくさんだった
徳川家康にあやかってみてはいかがでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()