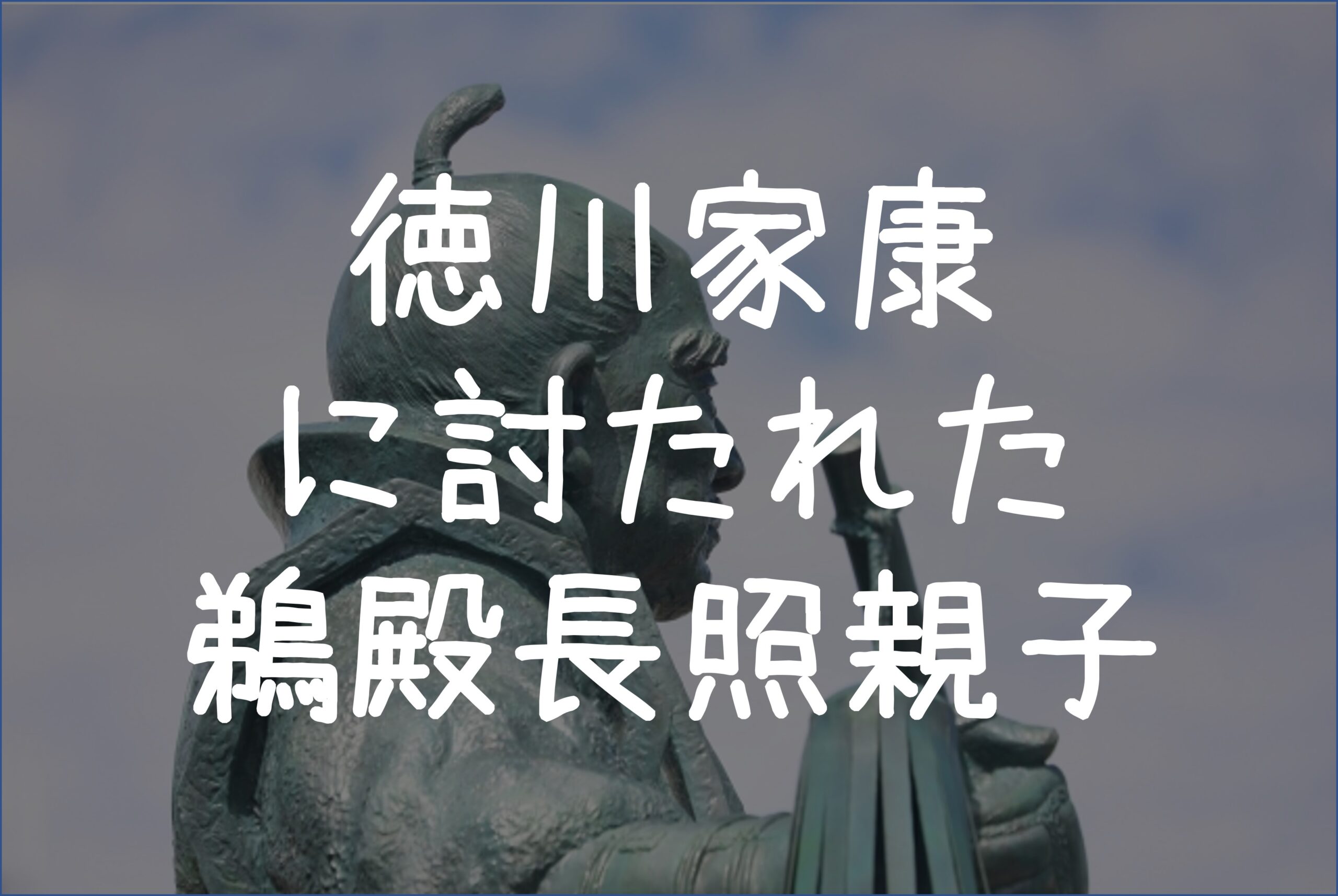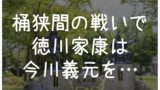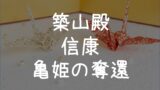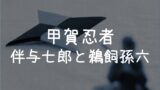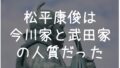今川家で人質となっていた家族を取り戻すため、徳川家康は、
① 今川家臣・鵜殿長照
② 鵜殿長照の子ども・氏長
③ 鵜殿長輝の子ども・氏次
の親子3人を捕らえることにしました。
徳川家康に討たれた鵜殿長照と人質になった氏長・氏次兄弟の生涯を紹介します。
徳川家康に討たれた鵜殿長照
鵜殿長照は今川家臣・鵜殿長持と今川義元の妹の間に長男として誕生しました。
上ノ郷城主となる
弘治2年(1556年)、上ノ郷城(愛知県蒲郡市)の城主を務めていた鵜殿長持が亡くなります。
跡を継いだ鵜殿長照は上ノ郷城主になりました。
② 鵜殿長照の弟・鵜殿長忠が城主を務める柏原城
は、今川氏が西(三河国)に領土を拡大するうえで、とても重要な拠点。
今川義元の甥である鵜殿長照と鵜殿長忠は今川家臣の中でも特に重用されました。
大高城代となる
天文20年(1551年)、今川義元は織田信長から大高城(名古屋市緑区)を奪いました。
大高城は織田信長の支配する尾張に近く、鵜殿長照は城代に任命されました。
大高城の兵糧は枯渇してしまいます。
鵜殿長照は、
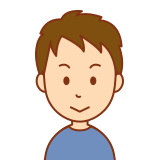
必ず援軍がやって来る!
と言って、城兵を励まし、草や木の実を食べて飢えを凌ぎました。
今川義元から命じられた徳川家康は織田軍の目を欺いて、大高城に兵糧を運び入れました。
飢えから解放された鵜殿長照は大高城の守備を徳川家康に任せ、今川家の本拠地である駿府に帰りました。
徳川家康に敗れて討死する
桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると、今川家臣は大混乱。
跡を継いだ今川氏真に求心力がなく、今川家を離反する家臣が続出します。
そして、近隣の松平家の領土の獲得に乗り出します。
鵜殿長照は上ノ郷城の南に位置する竹谷城の城主・松平清善と戦いました。
中には、松平清善に寝返る家臣もいましたが、鵜殿長照は戦いで優勢になりました。
今川家で人質となっていた、
① 正室・築山殿
② 長男・信康
③ 長女・亀姫
を取り戻そうと、鵜殿長照とその子ども・氏長、氏次の3人を生け捕りにしようとしていたんです。
永禄5年(1562年)、徳川家康の命を受けた甲賀衆により、上ノ郷城は混乱に陥り、鵜殿長照は討死しました。
人質になった氏長・氏次兄弟
紹介したように、鵜殿長照には、
① 鵜殿氏長
② 鵜殿氏次
の2人の息子がいました。
鵜殿氏長
父・鵜殿長照が上ノ郷城で討死すると、鵜殿氏長は弟・氏次と共に徳川家の人質となりました。
そして、今川家で人質となっていた徳川家康の家族と引き換えに、今川氏真に引き渡されました。

今川家に戻った鵜殿氏長は、小原鎮実と共に吉田城(愛知県豊橋市)を守るよう命じられます。
ところが、今川家には既に力がなく、永禄8年(1565年)、徳川家康に吉田城を攻略されてしまいました。

永禄11年(1568年)、「今川氏真に仕えていては未来がない」と判断した氏長は徳川家康に仕えることを選択。
二俣城の守将を務めた後、姉川の戦いや長篠の戦いなどに参戦しました。
天正19年(1591年)、徳川家康が関東に移封されると、1700石を与えられました。
① 徳川秀忠の養女・福正院(鶴姫)が姫路藩主・池田利隆に嫁ぐ際
② 同じく徳川秀忠の養女・保寿院が熊本藩主・細川忠利に嫁ぐ際
にお供するなど、戦以外でも活躍。
慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では使番として参戦し、寛永元年(1624年)に76歳で亡くなりました。
鵜殿氏次
鵜殿氏次は兄・氏長と共に吉田城を守っていました。
でも、徳川家康に吉田城を攻略された後、行き場をなくしてしまいました。
兄・氏長は徳川家康に仕えることを選択しましたが、鵜殿氏次は気持ちを切り替えることができませんでした。
天正18年(1590年)、考え抜いた末、鵜殿氏次は従兄弟・松平家忠に仕えることを選択。
慶長5年(1600年)の伏見城の戦いで、伏見城の守将を任された松平家忠に従い、鵜殿氏次は討死しました。
まとめ:鵜殿氏長・氏次は徳川家康に仕えた!
徳川家康に討たれた鵜殿長照と人質になった氏長・氏次兄弟の生涯を紹介しました。
徳川家康のターゲットとなっていた鵜殿長照、鵜殿氏長、鵜殿氏次。
3人には、今川家しか行き場がなかったのかもしれません。
鵜殿氏長、鵜殿氏次が徳川家康の元で活躍したことを、鵜殿長照はどのように思うのでしょうか。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()