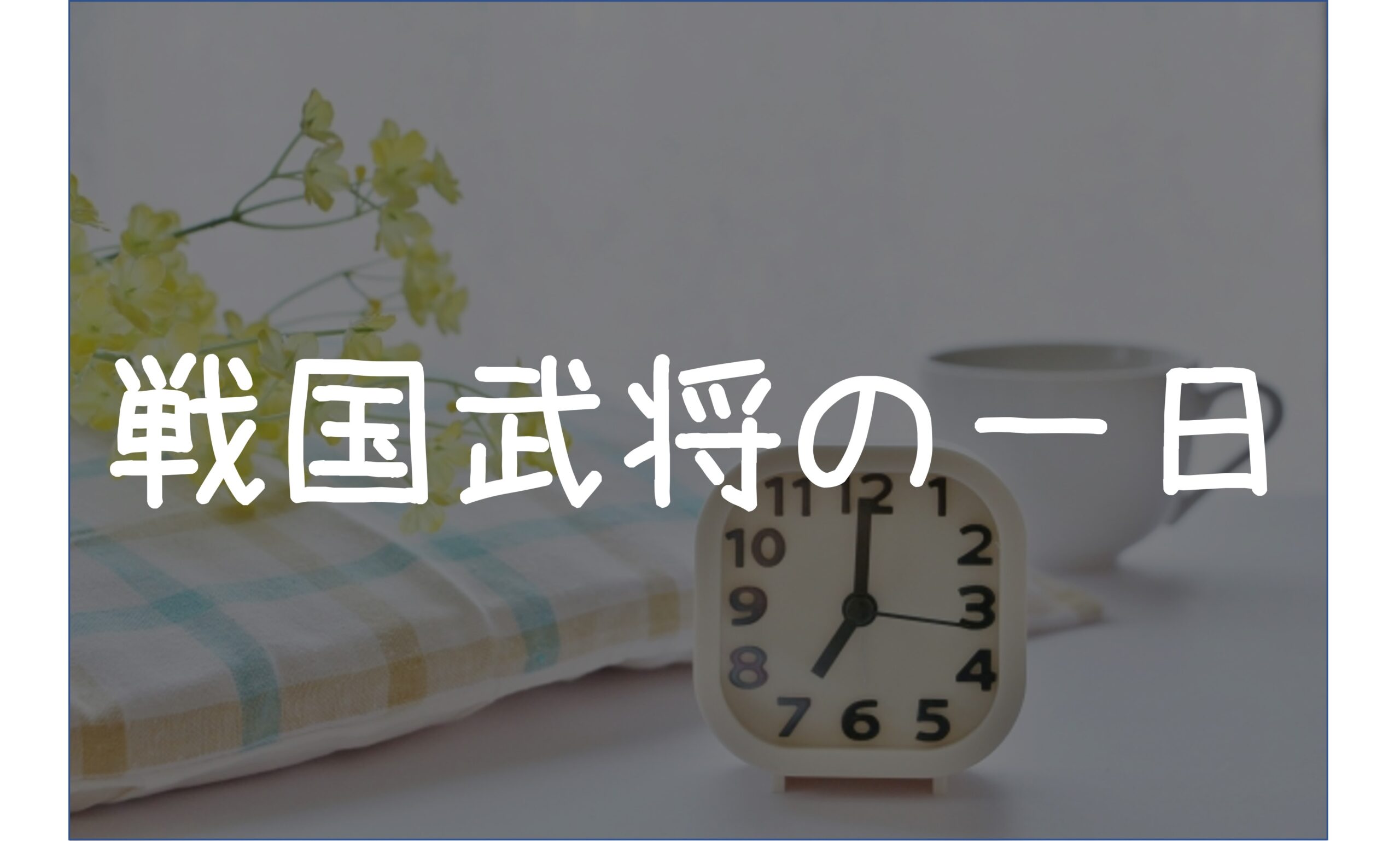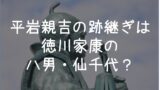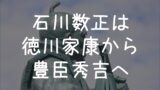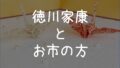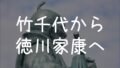戦の絶えない戦国時代。
戦国時代を生き抜くために、戦国武将はどのような生活を送っていたのでしょうか。
織田信長や徳川家康が送っていたかもしれない戦国武将の一日を紹介します。
起床する
戦国武将の朝は早く、寅の刻(午前3時から午前5時)に起床します。

何故、こんなに早起きだったのでしょうか。
その答えは身体を温めるため。
夜襲といえば、真っ暗な深夜に襲うイメージをもっている方もいらっしゃるかもしれません。
でも、実は、明け方に襲うことがほとんど。

万が一、夜襲されても敵を討ち迎えられるよう、早く起きて身体を温めていたんですね。
起きて最初にすることは、屋敷内外の点検です。
誰かが忍び込んだ形跡はないか、床が汚れていないかといったチェックを行いました。
☑ 誰かが忍び込んだ形跡がある
☑ 床に汚れがある
など、普段と異なることがあれば、家来に調べさせたり、掃除させたりしました。
屋敷内外の点検が終わったら、水を浴びて身体を清めます。
禍事(まがごと)や罪、穢れ(けがれ)を水で洗い清める禊(みそぎ)のような行為です。
この後、戦国武将は髪を結い直し、衣服を整えて、神仏に礼拝します。
心身を清めて、神仏、そして、自分と向き合うんですね。
朝食をとる
卯の刻(午前5時から午前7時)になれば、城に出仕します。
朝ごはんは自宅で食べて行きますが、もし、自宅で食べる時間がない場合には、お弁当を持って行きました。
・お弁当を持って出仕する場合には、主君や家臣と一緒に食事をする
などしました。
また、朝ごはんを食べながら、政務の打ち合わせをしていました。

時には、朝ごはんをアテにお酒を飲むことも。
今でいうビジネス会食をしていたんですね。
ほぼ毎日出社する現代のビジネスマンとは違って、戦国武将は毎日出仕していたわけではありません。
出仕しない日は辰の刻(午前7時から午前9時)頃に朝ごはんを食べていました。
仕事する
城に出仕する日は、主君から与えられた任務や役職に応じた仕事をします。
・右筆(ゆうひつ)は書類を作成する
・小姓(こしょう)は24時間体制で主君の身の回りのお世話をする
などしました。
小姓だった平岩親吉は大忙しだったに違いありません。
仕事がなければ、領地が抱えている問題の解決にとりかかります。
現代の日本では、人と人が争えば、法に則って解決していきます。
でも、戦国時代では戦に発展してしまうため、問題をみつけたら、早急に解決しなければいけませんでした。
戦には勝ち負けがあります。
勝てば、その地で堂々と暮らすことができますが、負ければ、その地を去らなければいけません。
民が領地を去れば、税収が減ってしまいます。
問題を放置してもいいことはないんですね。
出仕しない日や仕事のない日は畑仕事をしたり、家事を手伝ったりしていました。
戦国時代は当然電気もなく、現代社会のように便利な家電製品もありません。
力の強い男性はとても頼りにされていました。
身体を鍛える
仕事のない日はもちろん、仕事のある日は合間に武術を磨きました。
弓矢や槍、剣の扱いに慣れれば慣れるほど、戦で活躍します。
また、水泳や流鏑馬(やぶさめ)にも励みました。
戦で活躍することも大事ですが、いざという時には無事に逃げ切ることも必要。
海や川を泳いで渡ったり、馬を速く走らせたりできるよう訓練していました。
教養を身につける
戦国武将には、戦で武功をあげた者もいれば、軍略に長けた者、交渉に長けた者などもいました。

和睦しても、同盟を結んでも裏切られることのあった戦国時代。
腕っぷしがいいだけでは、戦国時代を生き抜けません。
隣国の大名や幕府、公家の心をつかめるよう、和歌や絵、花を学び、教養を身につけました。
来客に対応する
同じ主君に仕える戦国武将は同僚の家にお邪魔して打ち合わせすることも。
打ち合わせする時にはお酒を飲むことも多く、お酒や食事を切らさないよう、家人に指示していました。
来客のある日は、奥様が一番忙しかったかもしれませんね。
夕食をとる
私達は午後5時以降に夜ごはんを食べますが、それは部屋が明るいからできること。
電気のない戦国時代は、太陽とろうそくに灯す火が頼りです。
太陽が沈む前の未の刻(午後1時から午後3時)頃には仕事を終えて、夜ごはんを食べました。
仕事を終える
夜ごはんを食べた後は、家臣の相談に乗ります。
紹介したように、戦国時代は和睦しても、同盟を結んでも裏切られることがありました。
これは、家臣であっても同じ。
例えば、石川数正は徳川家康のもとを突然去って、豊臣秀吉に仕えました。
信頼関係を強めるためには、
・家臣の話をじっくり聞く
・家臣の相談に乗る
などして、コミュニケーションを密にとることが大事だったんですね。
家臣とコミュニケーションをとるのは、遅くても18時まで。
というのも、18時を過ぎると、辺りはすっかり暗くなり、自宅に帰ることができなくなるからです。
自宅に帰ることができる場合には自宅に帰ります。
もし、自宅に帰ることが危険だと判断した場合には、家臣は主君の自宅に泊まりました。
就寝する
家臣とコミュニケーションをとるという最後の仕事を終えたら、寝る準備をします。
酉の刻(午後5時から午後7時)には自宅の門を閉めて、屋敷内を見回って、火の元を確認します。
そして、戌の刻(午後7時から午後9時)には、布団に入ります。

紹介したように、戦国武将は寅の刻(午前3時から午前5時)に起床します。
午後7時に就寝すれば、午前3時に起床しても、睡眠時間を8時間確保できます。
睡眠時間を8時間確保していたら、戦国武将は私達よりも健康的な生活を送っていたのではないでしょうか。
身分の高くない者は交代で屋敷内を見回り、敵の不意打ちに警戒していました。
まとめ:戦国武将は想像以上に大忙し!
織田信長や徳川家康が送っていたかもしれない戦国武将の一日を紹介しました。
織田信長は明智光秀に討たれて48歳で亡くなりましたが、徳川家康は75歳まで生きました。
戦国武将のように、
・早寝早起きをする
・身体を鍛える
・学問に励む
などしたら、健康寿命を延ばすことができるのかもしれませんね。
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、こちらのDVDがオススメです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
ブログランキングに参加しているので、もし良ければクリックで応援をお願いします!
![]()